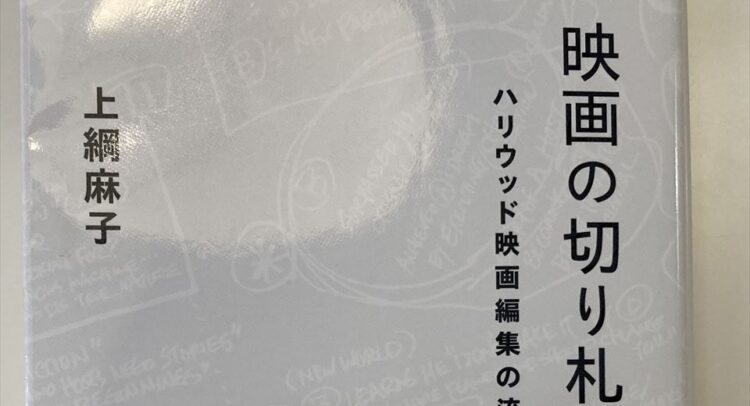上綱麻子氏の著書『映画の切り札 ハリウッド映画編集の流儀』を読んだ。
著者の上綱氏は、マイケル・マン監督・クリス・ヘムズワース主演の『ブラック・ハット』や、Netflix配信映画『マッドバウンド 哀しき友情』などで編集を担当している人物だ。アメリカで制作されたX JAPANのドキュメンタリー映画『We Are X』の編集も務めている。編集だけでなく、今年ディズニープラスで配信された真田広之主演の『SHOGUN 将軍』のコンサルタント・プロデューサーなんかもやっているような人物で、ハリウッドで長きに渡りキャリアを築いてきた方だ。
映像作品は編集が必要なものだとは、だれでも知っていることだろう。しかし、その良し悪し、重要性については素人には把握しづらい。撮影だったらカッコいいカメラワークや美しい照明があれば「おお!」と思えるわけだが、編集そのものは画面に映っているわけではない。画面に映す(残す)ものを取捨選択し、どのような順番で見せて、どんなリズムで提示するかを決めるのが編集なので、映画を観た時、編集そのものが眼前に見えるわけではない。本書は、そんな「インビジブルアート(隠れた芸術)」の奥深さをわかりやすく提示する内容だ。
日本と違うハリウッドの編集の仕組み
本書は、編集指南書のようなものとは異なる。著者が直近に手掛けているあるハリウッド映画の編集現場をドキュメントタッチで記しながら、その都度、編集者が何を考え、絵を選び、繋ぎ、時には順番を入れ替えたりしているのかを克明に記している。
映画の制作現場といえば、撮影風景を思い浮かべる人が大半であろうが、映画は撮影しただけでは全く完成しない。編集者によって映画がいかに変化していくのか、撮影された映像はいわばまだ「素材」であって、それをどう活かすのかを問われるのが編集者なのだ。
当然、監督の意向もあるわけだが、ハリウッドの編集者は組合の契約上、編集者の意向を優先できる期間が設けられているらしい。ハリウッドのポスト・プロダクションは以下のような流れになっているそうだ。(P46)
エディターズ・カット(一週間)
↓
ディレクターズ・カット(十週間)
↓
プロデューサーズ・カット(二~三週間)
↓
スタジオ・カット(プレビューを受けて実施)
↓
完成
エディターズ・カットは、基本的に監督にもプロデューサーにも干渉されずに編集者が自由に編集できる期間だそうだ。
そして、次にディレクターズ・カットで全米監督協会(DGA)が監督の創造する権利を守るために、最低十週間の編集期間を設けるよう義務付けているらしい(P47)。こういう編集のシステムはあまり語られていないかもしれない。
日本の場合は、こんなに余裕を持ったスケジュールではないはずだ。編集者だけがじっくりやれる時間というのは厳密には決められていないのではないか。アメリカと日本の編集スケジュールの違いは興味深い。
編集の現場はこんなにもエキサイティング
著者は、この編集作業の流れを日記のように、ドキュメントタッチで書いている。編集は撮影後から始まるのではなく、撮影ロケ地の近くに編集用のスタジオを借りて、そこで毎日の撮影素材を確認しながら、編集していく。今回の現場は、監督がしょっちゅう編集スタジオに顔を出すので、それだけ編集を重視する監督であると同時に、ちょっとや仕事しにくそうである。だれだって、ボスに見張られながらの仕事はしたくない。
そして、どんな心が目で撮影された映像と向き合って、どのテイクを使うのかなど、どんなことを考えているのかを克明に記録している。編集現場は絵として地味なので、メイキング映像でもあまり重視されない。絵としては地味だが、編集者の脳内では多くの戦いがあることを文章なら表現できる。編集現場のドキュメントは文字の方が向いているかもしれない。
こうして文字で読んでみると編集現場もなかなかエキサイティングである。突然プロデューサーから電話がかかってきて、撮り直しが必要か今すぐ編集して判断してくれ、みたいな事件が起きる。
撮影も残り三週間となって監督が「新しいエンディングを考えた」と言い出すあたりは、スタッフは振り回されて大変だと思うのが、物語としてはドラマチックである。「ここから一体どうなってしまうんだ?」とドキドキさせる。
この映画はまだ公開されていないので、実際に最終的な編集がどうなったかは、将来のお楽しみだ。読んでいて、早く答え合わせしたくなる瞬間がたくさんある。たんなる映像編集の解説書や技術やチップスを載せた指南書とは違って、「編集者のリアルな物語」として面白く読める。この本を読んでから、件の映画を観れたら、「あのシーンは最終的にはこうなったのか」と普段の映画鑑賞とは違った体験ができるだろう(公開前なので、映画の名前等は伏せられている)。
マイケル・マンの編集現場は過酷
本書には、マイケル・マンなどの巨匠も登場する。マイケル・マンの編集現場は相当に過酷だったことが伝わってくる。昨今、日本映画の労働環境問題の是正についての動きが活発になってきているので、アメリカの現場はどうなのだろうと気になっている人は多いと思うのが、本書にはその現場のリアルな空気も刻印されている。ハリウッドも、「大変な時は大変」なようだ。
その他、重要な映画監督としてディー・リースという人が登場する。この監督は日本ではそれほど知名度が高くないと思うが、とても素晴らしい作品を作っている作家なので、この本を機会に覚えてほしい名前だ。
一番有名な作品はNetflixで配信されている『マッドバウンド 哀しき友情』で2018年のアカデミー賞で数部門にノミネートしている。この映画で印象的なシーンは編集によって生まれたことが本書を読むとわかる。
もう一つディー・リース監督の重要な作品で『アリーケの詩』という作品がある。黒人のティーンエイジャーでレズビアンの女の子の成長と旅立ちを描いた作品で、インターセクショナリティを丁寧に描いた作品として、オスカー作品賞を受賞した『ムーンライト』よりも先駆けて制作された作品だ。多分、日本では配信オンリーで展開されている。この映画のラストシーンが編集によって生まれたことなどが、本書で書かれている。この編集で変わったラストシーンは、邦題の決め手にもなっているんじゃないかという気がする。原題は『Pariah』なのだが、詩を読む主人公の個性を活かしたラストになっているので。
ハリウッドに拭くアジアの風への複雑な眼差し
著者は、今年話題になったFXのドラマ(日本ではディズニープラスで配信)『SHOGUN 将軍』のコンサルタント・プロデューサーも務めている。本書も編集だけではなく、ハリウッドでアジア人として働くことへの記述が多く含まれており、昨今の「アジアブーム」に対する複雑な想いも垣間見える。
アジア人の女性として、多くの苦労も綴られており、それゆえに、仕事がしやすくなった昨今のアジアブームは歓迎すべきこと、しかし、一時の流行としてマイノリティ性を消費されているだけのような気もする・・・。アメリカにおける「多様性」に関する微妙な心持ちのリアルが表れている。
とはいえ、日本人としては明らかに追い風ではある。この追い風をいかに利用していくのか、今は大事な時期なのだということだろう。
『SHOGUN 将軍』はエミー賞最多部門ノミネートなど絶賛されたが、コンサルタント・プロデューサーとして、どう内容に貢献していたのかも綴られているので、あの日本描写がいかに成立したのか、興味ある人も読むといいと思う。