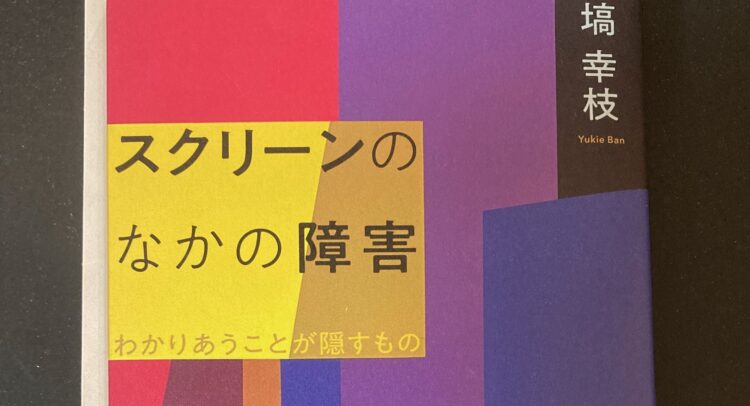フィルムアート社刊行、塙幸枝氏の著書『スクリーンの中の障害』は、大変素晴らしい本だ。
「障害」は物語の題材となりやすい。そもそも、物語は主人公に何らかの困難があり、それを乗り越えるという形で展開するのが定石だ。映画もこれまで様々な障害者をスクリーンに描き出してきたが、そのまなざしは時代とともに変化してきた。
本書は映画における障害の描き方の変化に着目した本だ。「はじめに」で早速アカデミー作品賞を受賞した『コーダ あいのうた』が取り上げられる。ここで著者は、『コーダ』を誉めつつも、「当作品への世界的な賞賛をもってして、「障害というテーマへの注目度の高まり」とか、ひいては「障害に対する社会的理解の促進」といった結論に結びつけることは、あまりに短絡的」と書く。
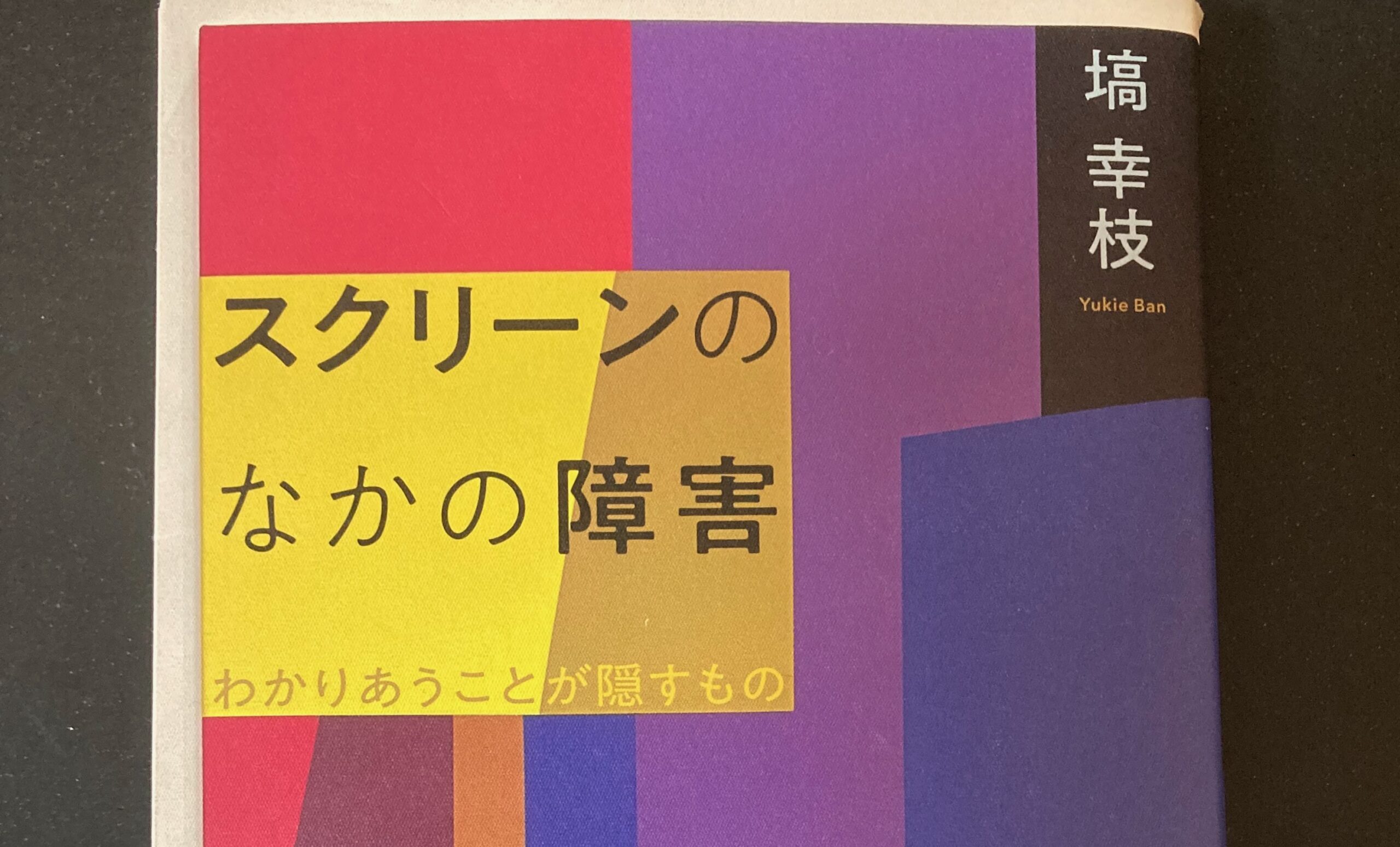
本書は、映画の中の障害者像はかつて差別や恐れの対象であったり、あるいは同情的であったりしたが、近年では「親和的」で「共生的」な障害観が提示されることが増えているとする。そして、その点について「手放しで賞賛されるべきものなのでしょうか」と疑念を呈している。「理解可能な存在」として障害者を描くあまりに、「わからないこと」や「理解できないこと」を覆い隠すことにもなるのではないか、より多様な側面があるにも関わらずそれが見えにくくなる可能性をまず、冒頭で指摘しており、これが本書全体の姿勢となっており、さらに、作り手の描写について批評・論評するだけでなく、観客の受け取り方についても踏み込んでいる。
映画の障害者イメージの変遷
本書は映画の中の障害者イメージのパターンを、まず3つに分類している。
1:モンスター化された障害者
2:非力化された障害者(脱モンスター化)
3:有能力化された障害者(脱非力化)
1の例として『フリークス』(1932年)が挙げられている、そして、1から2への過渡的作品としてデヴィッド・リンチの『エレファント・マン』が登場し、この頃から脱モンスター化とともに非力で保護すべき存在としての障害者像が顕在化してくるという。ここではイングマール・ベルイマンの『秋のソナタ』が例として挙がっている。3の例は『レインマン』や『フォレスト・ガンプ』だ。
著者は、有能力化された障害者像は、過去の差別的な表象の反省的態度という点で、必ずしも否定されるべきではないが、あくまで社会の中で有用かどうかを前提にしており、社会のメインストリームが絶対の価値として保持されているうえ、障害を能力主義に回収することで、個人の問題として矮小化してしまう可能性もあると指摘している(P76)。
著者は、障害を描く、解釈する点で重要な2つの概念を紹介している。障害を捉える2つのモデルがあるという。
医学モデルは、障害者個人に帰属する身体的・精神的な欠損としてとらえ、社会モデルは障害を「障害者に不利益を生じさせる社会的障壁」としてとらえるという。
上記3つの捉え方は、いずれも基本的に障害者個人の問題としてとらえる辺り、医学モデル寄りだが、近年は社会モデルとしてとらえる作品も登場しているとする。代表的な例として『最強のふたり』と『ワンダー 君は太陽』を紹介している。
『コーダ あいのうた』の無音描写の問題点
こうした歴史観と障害をとらえるモデルを提示した上で、著者はコミュニケーションの問題として描かれる障害、映画ならではの要素として「視覚的・聴覚的に再現される障害」の論を展開していく。
非常に示唆に富んだ内容が多いので、全ては紹介しきれないが、ここでは、冒頭でも言及されている『コーダ』の描写の評価を見てみる。当作品には、無音のシーンがある。主人公のコーダであるルビーの合唱発表会にろうの両親が観客席で眺めているシーンだ。ここで、映画は音をカットして無音にすることで、両親の聴取状態に観客を同一化させようとしている。
著者は、これを観客に聞かれることを前提にした演出であり、障害の再現をしたように思えても、結局は聴者が聞こえることに支えられたものであるとする。また、この演出は、音の喪失が「何もない」ことを意味し、ろう者が「見ること」で多くの情報を得ている現実を軽視する可能性を指摘している(P146)
こうした「安易な観客をろう者に同一化させる」試みるのとは別の方法でろうを描いた作品として『サウンド・オブ・メタル』が取り上げられているが、この分析も鮮やかなので、是非読んでいただきいと思う。もうひとつ三宅唱監督の『ケイコ 目を澄ませて』の「勝手に人の心読まないで」という台詞が作品全体が安易な共感や理解を拒んでいることを象徴しているとする。
障害者の役を健常者が演じることの是非ではなく可否
本書は、最後の章で障害を演じることについても示唆に富んだ理論を展開している。「障害者の役は障害者が演じるべきだ」という言説には、主に2つの側面がある。1つは機会平等や権利の観点で障害を持った俳優の活躍の場を開いていくべきという観点。もう1つは「リアリティ」だ。本書は、後者の観点で議論を展開している。これは、そもそも「リアリティとは何か」の根源を問う内容となっている。
そしてこの「リアリティ」の問題は、映画を作る側の姿勢だけでなく、観客側の意識の問題として捉えているのが特徴だ。健常者が障害者を演じる場合、ある人はリアリティがあったと評価し、別の人はリアリティがないと評する状況がある。これは、「障害者を演じること」のフィクションの境界線がある人には機能し、別の人には機能しないことがあるということだと、著者は語る。つまり、フィクションにおける障害の表象の境界線は一定ではない、このことを可視化するために、著者は、「障害者が健常者を演じること」を想定してみることを提案しているのが興味深い。
障害を持った人々は、障害者のリアリティの水準が健常者より高いだろう。では障害者が健常者を演じた時、社会の大多数を占める健常者はそのリアリティの水準をどう感じるか、そこに現前と横たわる「身体性の違い」に気が付くだろうとする(具体的にはNHKの『バリバラ』の実践が紹介されている)。
障害者の役を健常者が演じて良いのか、という問いは是非ではなく「可否」によって論じられていくことが望ましいと著者は結ぶ。この辺りの記述は大変に勉強になるので、是非多くの人に読まれてほしい。
本書は「描き方」だけではなく「受け取られ方」にも目を向けているのが出色だ。私たち観客はどう受け止めてきたのか、身体性の異なる人々のリアリティをどう受け止められるのか。万人が納得できる描写というのは、そうは成立しないものだとすれば、障害のリアリティをめぐる議論は、作り手だけを対象にしていたは足りないのだということがよくわかる。本書は、描写論にとどまらず「観客論」に踏み込んでいる点が出色だ。