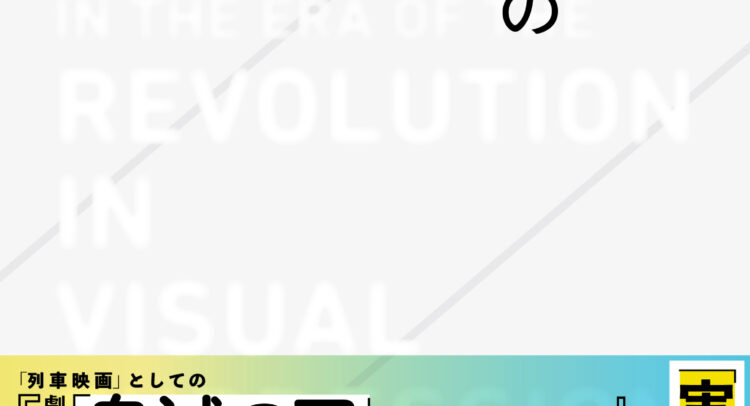リアルサウンド映画部に、実写とアニメーションの2つの領域で活躍する作家についてのコラムを書きました。
東映動画から『化け猫あんずちゃん』へ 実写とアニメを横断するクリエイターの歴史|Real Sound|リアルサウンド 映画部
拙著『映像表現革命時代の映画論』のテーマでもある実写とアニメーションの輪郭について、クリエイターの視点から見つめたような内容になっています。本では、出崎統監督や東映動画の歴史にはあまり触れられていなかったので、本の補完的な内容になったかなと思います。
昨年の『化け猫あんずちゃん』のように実写とアニメーションの監督による共同制作作品も今後増えていくといいですね。新しい刺激が得られると思うので。
以下、原稿作成時のメモと構成案。
——————
編集部の依頼に対して送ったメール
実写とアニメーション、双方で活躍するクリエイターに関するコラム原稿ですね。
日本アニメの歴史が本格的に始まったのが、実写の映画作ってた東映が東映動画作ってからなので、
初期のアニメ演出家は、実写出身なことも多かったんですよね。
その後、映画で名義貸しも含めて実写監督が劇場アニメの監督として名を連ねるケースが増え(ヤマトとか)、
庵野秀明がいて、原恵一が一度チャレンジして、最近はその越境をする人は、日本ではあまり多くないわけです。
一方、ハリウッドの大作映画ではCGアニメ出身の実写監督とか、あまり珍しくないですね。
実写とアニメに本質的な差異はあるのかという議論も踏まえつつ、日本における実写とアニメの越境の歴史をまとめるという形であれば、何か書けるかなと思います。
Point3つ
日本アニメの実写的演出の歴史
デジタルという結節点、しかし、そもそも元々は一つだった
これからの協業する時代に向けて
本広克行×谷口悟朗が語り合う実写とアニメの演出論 『踊る』と『プラネテス』の深い縁も|Real Sound|リアルサウンド 映画部
アニメはいかにレンズの効果を模倣してきたか – メディア芸術カレントコンテンツ
監督を務めた出崎統は『イージー・ライダー』(デニス・ホッパー 1969年)のレンズフレアがこの入射光の「原典」だといいます。
大塚さんの本から引用が必要・・・東映動画の実写出身の演出家の貢献について
METHODS 押井守・「パトレイバー2」演出ノート、、国会図書館
アニメーション監督出崎統の世界
Intro
今年のソニック映画を観た。相変わらず画面の半分近くがCGで占められていて、これは実写か否か?という問いを突き付ける作品であった。
『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』も監督したジェフ・ファウラーは元々短編アニメーションで注目された人。彼のCGアニメーションへの造詣の深さがシリーズの成功を支えている。
昨年の日本映画『化け猫あんずちゃん』はアニメーション監督と実写監督の共同作業による作品で、実写監督の山下監督のテイストが色濃く反映されたアニメーション映画として成立していた。
日米ともに、実写とアニメを区別する意味は、とりあえずのジャンル分けという程度の意味しかもはやないと筆者は思っている。
作り方も接近すれば、作家たちも近づきつつある。それぞれの分かれていた領域において、新たな刺激が得られていく。それは歴史的にも必然である。
Body1日本アニメの実写的演出の歴史
ディズニーとの差異を確認するところから、日本の商業アニメが始まっている面がある。
大塚さんの本から、東映動画時代の実写の演出家が多かった話から入る
作画汗まみれ、巻末論文:60年代頃の東映動画が日本のアニメーションにもたらしたもの 高畑勲
ディズニーはどうだったか:その画面は、人物たちが縦横に活躍できる舞台(世界)としてきちんと三次元の空間を作るが、絵画スタイルとしては現実的であるよりは夢のあるおとぎ話的雰囲気をかもしだす。
実写映画でも、そして、このような闘争型の作品でなくても、当時の一般的な日本の映画観客は、「枝葉」の笑いや「遊び」の要素(いわゆるエンターテインメント)を楽しむよりは、むしろ本筋の劇的展開や主人公の運命に一喜一憂することを喜ぶ(それをある種のエンターテインメントとする)という傾向が強かった。
主人公たちに感情移入させるためには、演出も、絵による「面白おかしい見世物的」演出よりは、主人公に寄り添ったいわゆる映画的な演出が要求される。この点、東映動画の演出家は、薮下泰司氏をはじめ、全員がアニメーター出身でない人々によって占められ、新東宝出身の芹川有吾氏や急激な映画産業斜陽化によって東映京都撮影所から流入した実写映画出身者が多かったことには意味があったかもしれない。なお、初期作品には、東映の撮影所から実写のベテラン編集者や監督が呼ばれて最終編集に関与することもあった。
いわゆるアニメーションらしい「遊び」にかまけるよりも、むしろ、作品世界に没入させるために、劇的な構成や表現で現実感実在感を与えることを基本とする。<中略>そのためにもカメラアングルやショット構成などを重視した、リアルな迫力を出す映画的演出を心がける。
↓
レンズを意識するのが当然の演出スタイルとなる
出崎さん
アニメはいかにレンズの効果を模倣してきたか – メディア芸術カレントコンテンツ
監督を務めた出崎統は『イージー・ライダー』(デニス・ホッパー 1969年)のレンズフレアがこの入射光の「原典」だといいます。
絵だけでなくカメラを用いて劇的な演出効果を生み出したのが出崎氏だった。そこには実写映画からの発想が多々あることが伺える。
↓
押井守の言葉
パトレイパー2のレイアウトでも、レンズのチョイスの重要性について語る。
こうしたスタイルが日本アニメの演出の基本路線となっている。実写的(映画的)な演出は、日本アニメの伝統と言えるもの。
↓
デジタルの地平で全ての映画はアニメになるという押井守の言葉
庵野秀明の登場、、実写とアニメーションのハイブリッドジャンルともいえる特撮に特異性を見出している。
自分の本から引用するか
↓
山田尚子や新海誠など、レンズ的、実写的な意識の絵作りは珍しくなく、3Dレイアウトの一般化もあって全面化しているといってもいい。
↓
海外においては、マトリックスのようなアニメから大きな影響を受けた作品が登場し、その垣根が崩れている。
全編モーションキャプチャを用いて、CGのキャラクターを動かす『アバター』のような作品も登場している。
自分の本から引用するか。
↓
今日、実写とアニメを区別する意味は失われつつある。
↓
元々、同じものである、先祖返りしたとみてもいい。
そもそも、サイレント映画時代には、両者はもっと近い存在で、チャップリンのコメディ映画は動きに芸術で、変幻自在にカメラのフィルムの速度を変えて動きを創造していた。
実写とアニメーションに分かれる原初性が、そこにはあり、それは坤為地デジタル化によって再び両者が分かれていない状態に立ち戻りつつあると筆者は自著で主張した。
↓
映像は、写真でも絵でもいいが静止画の連続で構成しているという点で、実写もアニメも違いはない。
それでも素材の調達の仕方によって感性が分かれていた部分がデジタル化によってつなぎ直されたと筆者は考えている。
そして、それはAI時代にますます進行していくと考えている。と自著で説明した。
Body2実写とアニメの領域で活躍する人たち
歴史を振り返ると、実写とアニメ両方で活躍してきた作家は、それなりにいる。
日本においては、一時期に、興行の箔をつけるために実写監督を招へいするという起用の仕方もあったにはあったが、その中から重要な作品、意欲的な作品が登場したことも確か。
昔、実写の監督が劇場アニメの監督を引き受ける事例はあった。だが、それは多くの場合名義貸しに近いものだったとも言われる。
有名なところでは宇宙戦艦ヤマトの監督が舛田利雄が有名だ。
サントラ千夜一夜 / 腹巻猫(劇伴倶楽部)第180回 愛の映画 〜少年ケニヤ〜 | WEBアニメスタイル
前述の庵野秀明や押井守は、自ら実写作品の企画を立ち上げて両輪で活動している。
アメリカでもティム・バートンやウェス・アンダーソン、ギレルモ・デル・トロのような3大映画祭で受賞するクラスの名監督に、両方の分野で活躍する作家がいる。
CG出身の監督はハリウッドでは珍しくない。
垣根の崩れた昨今では、ハリウッドではアニメーション出身の監督はめずらしくない
ブラッド・バード:『ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル』
ディーン・デュボア:ヒックとドラゴン
ジェフ・ファウラー:ソニック
アンドリュー・スタントン:ジョン・カーター
フィル・ロードとクリス・ミラー:21ジャンプ・ストリート
日本でも、CGに詳しいことで実写映画領域で活躍する作家としてこの2人がいる。
山崎貴:
曽利文彦:ピンポンなど
これは、デジタルの扱いに長けていないと実写作品も作れない時代になってきていることが関係している。
アニメから実写へ、CGが変える映画監督のキャリアパス:アニメビジネスの今(1/4 ページ) – ITmedia ビジネスオンライン
Body3
全てをデジタルデータとしてとらえ直す映像のデジタル化は、CGアニメーションとデジタルカメラで撮影した素材の垣根をなくしている。
では、手描きアニメの領域で今後いかなる協業があるか。
↓
実写とアニメ監督の協業
化け猫あんずちゃんは、実写監督の山下監督のセンスが全面的にでていた
ロトスコープという手法ならではな部分もあるかもしれないが、アニメに新鮮なセンスを導入する方法として実写の監督との協業は悪くない
↓
久野さんは、花とアリス殺人事件でも、岩井監督のテイストを忠実にアニメーションとして発揮させていた。
今後、日本のアニメ、実写ともに新たな血の導入として、協業していくのがいいのでは。
————-
メモ終わり。
日本アニメの発展の歴史は、実写からの影響は外せない要素です。もっと両方を横断して、区別しない批評のあり方が必要だと僕は考えています。
その考えを反映させたのは下の本です。ぜひ読んでくださいね。