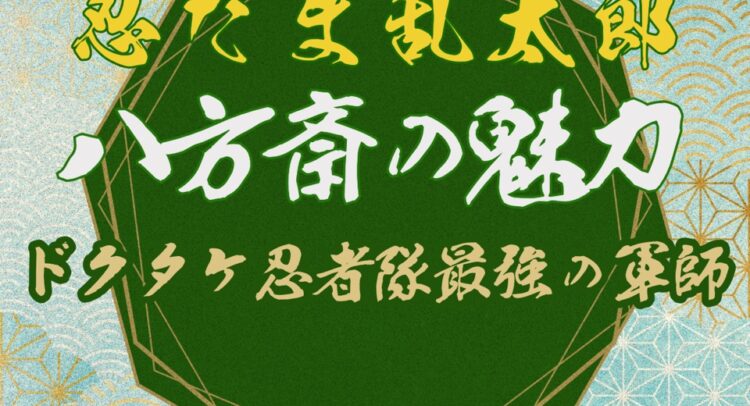アニメ!アニメ!の敵役連載に、『忍たま乱太郎』の八方斎を取り上げました。
「忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」八方斎の変貌が物語る、悪役が作品のトーンを形作る可能性 | アニメ!アニメ!
稗田八方斎 (ひえたはっぽうさい)は、乱太郎シリーズには欠かせない悪役です。いつもはドジで間抜けで、たまに切れ者で憎めない感じの悪役です。乱太郎やきり丸たちともなんだかんだで顔なじみみたいになっていて、観ていて安心できるというか、いつも大事なところでドジってくれるので、そんなにドギマギしなくてもいい悪役ですよね。
ところが、今回の最新劇場版『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』では、いつもと様子が違っていましたね。土井先生と頭を打ってしまったために、土井先生は記憶を失い、八方斎は頭が冴えていつもよりも残忍になっていました。
この八方斎の変貌ぶりが、今作には重要だったと思います。いつもはドジ踏む悪役が今回はガチで来ているということで緊張感が生まれているなと。
今回の連載では、そのあたりから悪役によって作品全体のトーンが決定づけられているという論を展開してみました。前回書いた、荒木飛呂彦先生の漫画術の悪役の作り方にも通じる部分がある内容になっています。
以下、原稿作成時のメモと構成案。
—————-
Thesis
今回の劇場版で見せた非情な側面とチャーミングさのギャップについて
Point3つ
いつものチャーミングで憎めない魅力、、、悪役が作品の哲学を決めるのか
今回、この男がいつもと違うからこその物語
そして、いつもの賑やかな感じに作品全体が戻るのに合わせて、彼も戻る、、部下ににもいつもと違うと心配されている、いつもの彼はなんだかんだ部下に慕われている
↓
作品の方向性に大きな影響を及ぼすキャラだ。
Intro
小さい子どもたちに向けたアニメ作品では、悪役もあまり怖くしてはならない。
悪いやつでやっつけられるけど、どこか憎めない愛嬌が求められる。
憎めない悪役の代表格である八方斎。
しかし、今回はいつもと様子が違った。
土井先生がいつもと違うことが描かれるが、同時に八方斎もいつもと違うのが、作品のポイントとして大きな要素になっている。
悪役が作品の哲学を形成するという、典型ではないか。
Body1いつもの八方斎の魅力について
いつもはちょっとドジで憎めない悪役、、忍たま学園の連中ともなんだかんだ仲良さそうにしている時もある。
その大きな頭をのけぞらせて、すっころぶというのが定番の、怖くない悪役だ。
でも実力はあると認められている。
部下思いで慕われてもいる。
忍術学園とは対立関係にあるが、どぎついことはあまりしない。
憎めない悪役として、ほのぼのした本作の雰囲気作りに大きな役目を果たしている。
Body2最新作の劇場版で見せた非情な側面
そんな八方斎が、今回の劇場版では違った面を見せる。
記憶を失った土井先生に、乱太郎たちを切り捨てるように命じたりする。
いつにも増して冴えているのは、彼も頭を打っていつもと違う八方斎になっているからだ。
冴えた八方斎は恐ろしいというイメージを作っている。元々実力者なので。
部下たちもドン引きする非情さ。
本作がいつもと異なる雰囲気を持った作品であることを踏まえると、八方斎の悪役としてのあり方がそれに大きな影響を与えていると言える。
土井先生が元に戻るのと一緒に、かれもいつもの八方斎に戻る。部下は安堵している。
それで、作品全体の雰囲気もいつもの感じに戻っていく。
悪役の作品全体への影響力の高さについてよくわかる内容の作品であり、悪役が作品の哲学を構成するという好例だ。
————–
メモ終わり。
『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』はとても面白い作品です。いつもと異なる雰囲気ではありますが、最後はいつもの『忍たま乱太郎』に戻っていくのがいいですね。八方斎もいつもの感じに戻ります。それでやっと、安堵感が生まれるというか。
良質なキッズムービーに必要な要素を兼ね備えて良作でした。このレベルの映画が毎年作れるのであれば、毎年やってほしいですね。
関連作品