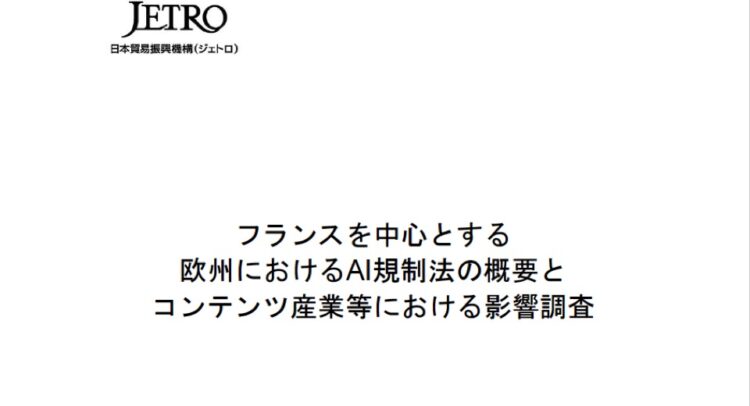JETROが「フランスを中心とする欧州におけるAI規制法の概要とコンテンツ産業等における影響調査」のレポートを掲載。その概要をまとめてみた。
EU主導のAI規制がコンテンツ産業に波紋、フランスの積極的なAI戦略と日本の動向
日本貿易振興機構(ジェトロ)パリ事務所が2025年3月に発表した調査レポートによると、進化を続ける生成AIの利活用において、知的財産権保護の重要性が高まる中、EUが2024年5月に世界に先駆けてAI規制法を制定した。本稿では、欧州におけるAI規制法の概要、フランスを中心とする生成AI関連政策、そして日本の現状について詳報する。
生成AIの定義と市場規模
レポートでは、AI規制法に基づき、AIシステムは「インプットから予見、コンテンツ、推奨事項、決定などのアウトプットを生成しうる機械ベースのシステム」と定義される。特に、コンテンツ生成を主目的とするものが生成AIと位置づけられ、テキスト、画像、動画、音楽などが含まれる。仏公的投資銀行Bpiフランスは、生成AIを「包括的かつ多目的なやり方で人間の知覚的能力を複製することができる」技術と捉えている。
世界のAI市場規模(生成AIに限らない)は、2024年時点で2,980億米ドルに達し、2030年には1兆8,470億ドルへの急成長が見込まれる。一方、世界の生成AI市場は、2023年の670億ドルから2032年には1兆3,040億ドルへと飛躍的な成長を予測されている。国別に見ると、米国が最大の市場であり続け、中国、ドイツがそれに続く。資金調達額では、フランスはEU加盟国内でトップ、英国がEU諸国を大きく引き離している状況だ。
EUにおける生成AI関連政策・AI規制法
EUは、AIの発展と展開には市民の理解と信頼が不可欠であるとし、EUの価値観と基本的人権に基づいた規制枠組みの構築を目指し、2024年5月にAI規制法を制定した。この規制は、AIがもたらすリスクの程度に応じて分類され、「許容できないリスク」「ハイリスク」「透明性確保を必要とするリスク」「最小リスク」の4段階で管理される。
特にコンテンツ産業に関わるのは、「透明性確保を必要とするリスク」に分類される生成AIだ。これらのAIを開発する企業は、技術文書の提供、コンテンツがAIにより生成された旨の明記、違法コンテンツ生成の防止措置、AIトレーニングに使用された著作権データの詳細公表などが義務付けられる。AIを用いて生成・変更されたコンテンツ(ディープフェイク等)は、AI生成であることの明確なラベル表示が求められる。
注目すべきは、EU域内に所在しない企業であっても、開発者/プロバイダーであれば規制の対象となり、日本企業も例外ではない点である。また、EU域内で利用されるコンテンツの生成過程でAIシステムを利用している場合も適用対象となるため、アニメの劇伴音楽の作曲にAIを利用するケースなどが該当する。
フランスにおける生成AI関連政策および関連プレイヤーの動向
フランスは、AI規制と支援のバランスを重視する立場を取りつつ、積極的にAI戦略を推進している。2018年のAI戦略第一弾では、研究開発体制の構築とエコシステムの整備に注力し、第二弾(2022年開始)では、AI技術の経済全体への普及を目指し、人材育成、技術支援、需給の連結を軸とした。
2025年にはAI戦略第三弾が始動し、コンピューティング・インフラの強化、人材育成・誘致、AI利用の加速、信頼性のあるAI構築に重点が置かれる。特にデータセンターの誘致に力を入れており、電力供給の強みを活かし、大規模なデータセンター建設を推進する。
フランスには、Mistral AIのような有望なスタートアップ、Sopra SteriaやThalesなどの大手企業、そして複数の「AIクラスター」が存在し、産学官連携によるAI研究開発が進められている。政府は、「フランス2030」などの投資計画を通じて、これらのプレイヤーへの資金援助を積極的に行っている。
また、フランスはAI規制法の施行に向けて、国立AI評価・安全研究所(INESIA)を設置するなど、安全性と信頼性の確保にも取り組んでいる。
日本の現状
日本においても、2022年以降、「AI戦略」の決定や「AI事業者ガイドライン」の公表など、AIに関する戦略・政策が進められている。2024年にはAI制度研究会が発足し、法規制も視野に入れた検討が開始され、2025年2月には「AI関連技術の研究開発と活用推進法案」が国会に提出された。
経済産業省は、GENIAC (Generative AI Accelerator Challenge) を立ち上げ、生成AIを開発する企業への支援を行っている。NTT、ソニー、富士通などの大手企業や、neoAI、sakanaAI、ELYZAといったスタートアップが、国産生成AIの開発を進めている。
まとめと提言
EUのAI規制法は、コンテンツ産業を含む広範な分野に影響を与える可能性があり、日本企業もその動向を注視する必要がある。特に、EU域内でAIを活用したコンテンツを提供する場合は、透明性義務などを遵守することが求められる。
日本のコンテンツ企業は、自社の製品・サービスにおけるAIの利用状況を確認し、EUのAI規制法が適用されるかどうかを検証すべきである。現時点では、EU当局によるガイドラインやテンプレートの発表を待ち、より正確な情報に基づいて対策を講じることが賢明である。
ソース:フランスを中心とする欧州におけるAI規制法の概要とコンテンツ産業等における影響調査(2025年3月) | 調査レポート – 国・地域別に見る – ジェトロ