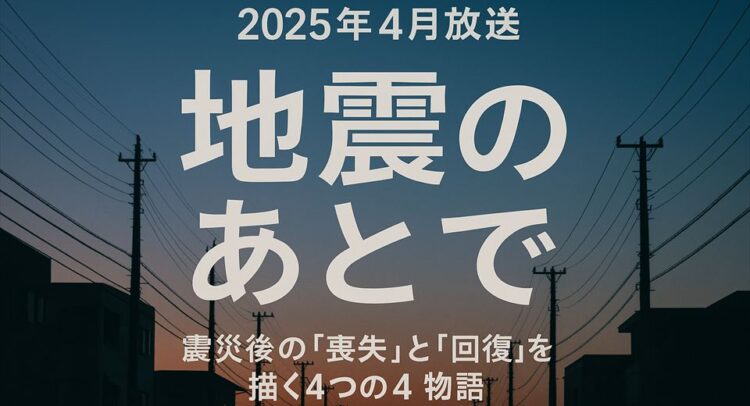NHKドラマ、村上春樹原作の4つの物語『地震のあとで』2話は、「アイロンのある風景」というタイトルのエピソードだ。出演は堤真一、鳴海唯、黒崎煌代。
第一話は阪神大震災直後のエピソードが描かれたが、今度は時代が一気に飛んで2011年の物語だ。阪神大震災発生から16年目の1月から3月11日早朝までの物語だ。
16年立っても喪失に向き合い続ける男と、空っぽだという女性の、焚き火を通じた問答が物語の中心になっている。
2011年東日本大震災直後の物語
舞台は茨城県。順子(鳴海唯)は、父親と上手くいっていないことで家を出て、適当に流れ着いた町で暮らしている。そこで出会ったミュージシャン志望の啓介(黒崎煌代)と同棲している。啓介は軽い男だが、付き合いも良くて明るい性格のいい奴だ。どうしもようもなく俗っぽいが、むしろ、この作品においては、彼が良心的存在として救いにもなっている。
順子は、コンビニでバイトしているが、そこの常連の三宅(堤真一)が、ある日、夜の海で焚き火をしているのを見つける。三宅はここで毎日のように流木を集めて焚き火をしているらしい。それにどんな意味があるのか、よくわからない。三宅自身にもよくわかっていないのだが、この町に来たのは、焚き火をするためなのかもしれないと三宅は言う。
夜の海で明かりは焚き火だけ。それを囲む三宅と順子の顔が炎でオレンジ色に薄ぼんやりを輝いている。この詩的な雰囲気が良い。
三宅は火の形は自由だという。それがどう見えるのかは、見る人の主観が反映されるのだと。焚き火の動きを見ているだけでも面白い。確かにどの瞬間も同じ形はしていない。絶えず不確実にその形状を変え続けるその様は生き物のようでいて、何かを語りかけてくるかのようでもある。
この焚き火の「パチパチ」という音と、波の音の自然音が心地良い。サウンドデザインの優れたエピソードだと思う。
焚き火は何を表すのか?
三宅は神戸からやってきたという。東灘区に住んでいたが、震災で妻と子どもを失った。なんで自分だけが生きているのかとよくわからない気分のままここまで生きてきた。焚き火で何を燃やしているつもりなのだろうか、それは供養か、自分の自責の念を昇華させようとでもいうのか。
とにかく、三宅は焚き火をしなくてはならないのだと思っている。順子に一緒に死ぬか?と問いかける宮家。そして順子はいいよ、でもちょっと眠らせてと言う。三宅は焚き火が消えれば、寒くなって嫌でも目覚めるという。このやり取りはなんだろうか。
焚き火が消える、目覚める。生き返る、ということだろうか。焚き火は喪に服す的な意味会いの、送り火と考えるのはシンプルでいいのだけど、ややシンプルすぎるかもしれない。
2011年3月11日早朝で幕を閉じる物語
タイトルの「アイロンのある風景」というのは、三宅が描いている絵のこと。このアイロンは実はアイロンではないのだと三宅は言う。順子は「アイロンはなにかの身代わりなんだね」と意味深な事を言う。
身代わり。三宅が生きているのは、家族が身代わりになって死んだからなのか。ここにいる自分は嘘の自分か。
物語は2011年3月11日の早朝を迎えて幕を閉じる。この日、何が起きるのか、僕らは知っているわけだけど、焚き火が目が覚めたら、未曾有の事態に見舞われる。
あの体験は、日本が何か別のものに変わってしまったような、そんな出来事だったかもしれない。焚き火が消えて目が覚めるというのとつなげて考えてみると、何か意味深な雰囲気になってくる。
登場人物
順子(鳴海唯)
啓介(黒崎煌代)
三宅(堤真一)