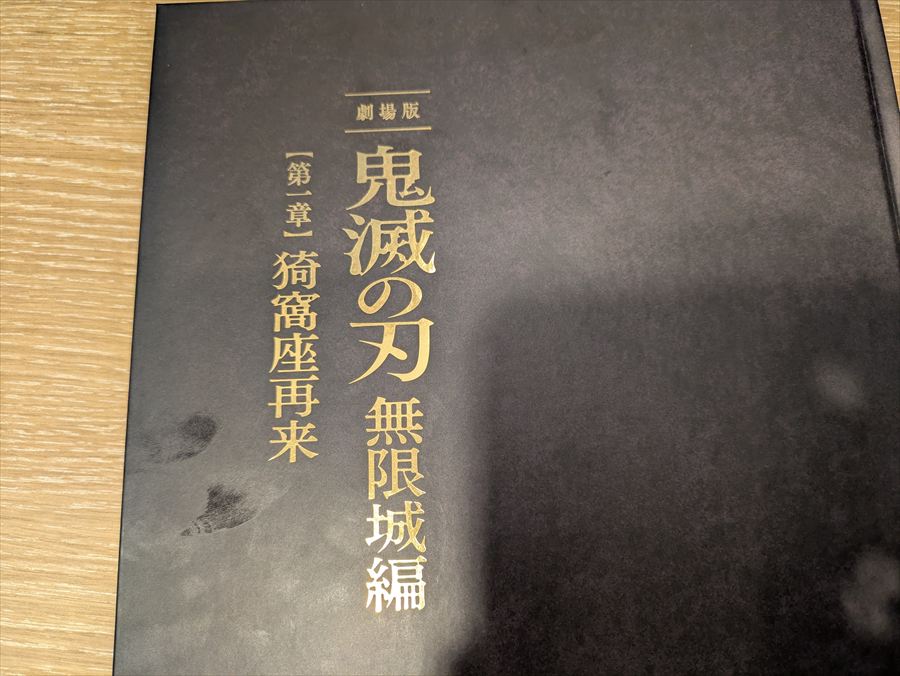ついに『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開された。上映時間155分という長さを全く感じさせない、驚くべき密度の映像体験は、単なる人気シリーズの続編にとどまらない。本作は、壮絶な戦いを通じて「鬼とは何か、人間とは何か」という根源的な問いを突きつけ、登場人物たちがそれぞれの過去といかに向き合うかを描ききった、物語の最終局面に相応しい重厚な一作であった。
因縁渦巻く総力戦と多層的な物語
本作で描かれるのは、胡蝶しのぶ対童磨、我妻善逸対獪岳、そして竈門炭治郎と冨岡義勇対猗窩座という、原作でも屈指の人気を誇る三つの決戦である。しかし映画は、単に原作のエピソードをなぞるだけではない。それぞれの戦いが深い「因縁」に根差した、避けては通れない魂のぶつかり合いであることが、より一層強調された構成となっている。
とりわけ、虫柱・しのぶの戦闘が本格的に描かれたが、虫のイメージ描写がすごく異質を放っていていい。対する童磨の話が通じない感じが宮野真守の芝居でかなり具現化されていて、不気味だった。
さらに注目すべきは、無名の平隊士たちの奮闘にも光が当てられている点だ。一部の強者である「柱」だけでなく、鬼殺隊という組織が総力を挙げてこの決戦に臨んでいる様が描かれる。これにより、個々の因縁の物語が、人類の存亡をかけた大きな戦いのうねりへと繋がり、物語に多層的な深みを与えている。原作の行間を巧みに膨らませ、巨大な空間で多くの者が死闘を繰り広げていることを強く意識させる構成は見事である。
圧巻の舞台装置「無限城」
今回の戦いの舞台となる「無限城」の描写は、圧巻の一言に尽きる。これだけでとんでもない予算が投入されていることは想像に難くない。
物理法則を無視して絶えず構造が変化し、方向感覚を奪う悪夢のような空間。制作陣は、この異様な空間を映像化するために尋常ならざるこだわりを見せている。公式パンフレットによれば、そのあまりの物量から、全リソースを投入してもレンダリングに3年以上を要する試算となり、急遽機材の大規模な増設やインフラの見直しまで行われたという。
このこだわりは、観客にキャラクターたちが置かれた状況の絶望的なスケールを体感させることに成功している。広大さとギミックの豊富さは、見ているこちらも迷宮に迷い込んだかのような錯覚を覚えさせる。無限城は、もはや単なる背景ではなく、本作のテーマを象徴する重要なキャラクターの一人と言えるだろう。この舞台装置を隅々まで見るだけでも価値がある。
最高峰のアクションと、魂を揺さぶるドラマ
本作は、「全編アクションの嵐」である。複数の決戦が同時並行で進行し、息つく暇も与えない。そのクオリティを支えるため、戦闘パートごとに4人のアクションアニメーターがリーダーとなり専門のアクション作画チームを立てたという。それによって、一つ一つの戦いが見せ場の連続となり、観客をスクリーンに釘付けにする。
しかし、本作が155分という長尺を必要とした理由は、アクションシーンの物量だけではない。むしろ、上弦の参・猗窩座の人間時代の過去をはじめとする、登場人物たちの感動的なエピソードにこそ、たっぷりと時間が割かれている点にある。
特に、猗窩座がなぜそこまで「強さ」に固執するのかを解き明かす過去の物語は、一切の省略なく、丹念な演出で情感豊かに描かれる。この丁寧な描写によって、猗窩座は単なる「倒すべき敵」から、悲しい過去によって運命を歪められてしまった一人の「人間」として立ち現れる。彼の過去を知ることで、観客は鬼という存在の悲劇性に触れずにはいられない。
このあたりの描写に、鬼になることと人間としてとどまることをめぐる本作のドラマの核心があるような気がする。この世界は理不尽で不平等だ。それをひっくり返す力が欲しくないかと言われたら、だれでも心がぐらつく。それでも鬼にならずにふんばるのが炭次郎に代表される鬼殺隊であり、その誘惑に負けたのが鬼になった連中だ。どちらも等しく社会の理不尽は経験しているのだ。
戦闘の迫力と、魂を揺さぶるドラマ。本作は、その両輪が極めて高いレベルで融合している。重要な要素を何一つ削ることなく、物語が本来必要とする時間をかけてじっくりと描くという制作陣の選択が、単なるエンターテインメント大作ではない、人の業と悲しみ、そして失われた人間性を描いた重厚な物語を完成させた。映画館で体験すべき価値を持つ作品に仕上がっている。155分もあっという間に感じられる内容だった。