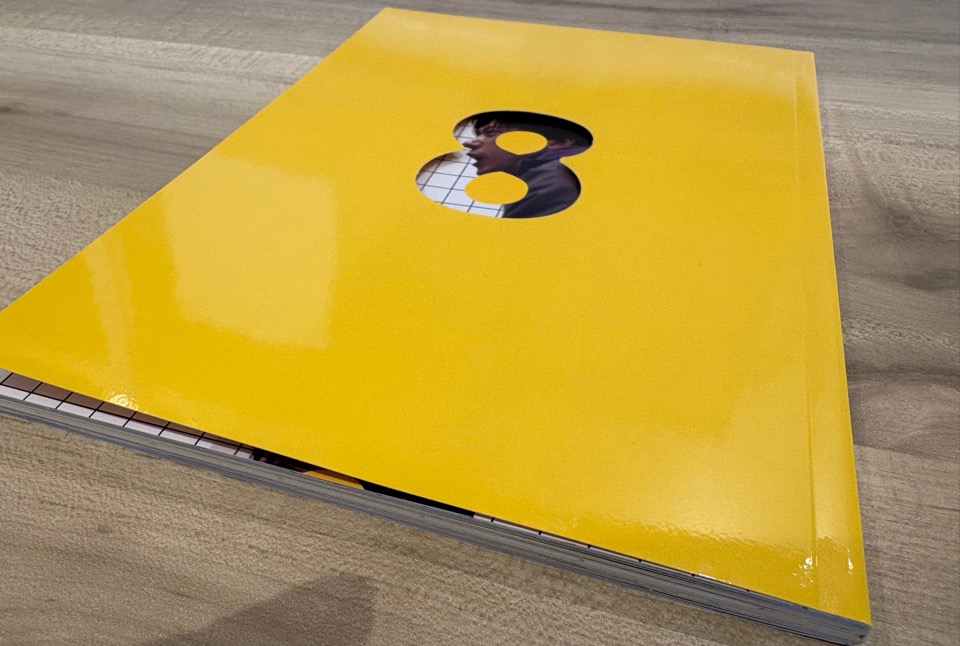投票で決まった映画の月イチレビュー、今回は『8番出口』をやっていきましょう!
月イチで書く後半ネタバレありの映画レビューはどれがいい?のアンケートです。結果が見えているような気もするけど3つ目だったらどうしよう…。
— ヒナタカ@映画 (@HinatakaJeF) August 27, 2025
個人的にお気に入り度:8/10
映画.com:3.3/5 Filmarks:3.5/5
本作については以下の記事にも書きました。ネタバレなしなので鑑賞前にどうぞ(公式からアナウンスされた注意喚起もごく短く追記しました)↓
目次
ネタバレなしの前置き1:否定的な意見に納得できる特徴は?
世間的に映画『8番出口』の評判はなかなかに賛否両論ですが、それにも納得もできます。
その理由の筆頭が、ホラーとして怖い以上に、意図的にせよ観客に強いストレスを与える作風であること。「嘔吐」の描写があるほか、後述する通り、「喘息の咳き込み」や「赤ちゃんの鳴き声」にはちゃんとした意味があると思うのですが、「延々と続くループに閉じ込められる」シチュエーションも相まって、過剰にツラく思えてしまう人もいるのも致し方ないかなと。
さらに、これもまた意図的ですが、そもそもが不条理な設定のため理屈では納得できない部分があることと、種々のシーンの解釈がはっきりしていないところがあること。それなりに明確なポイントもあるにはあるのですが、一方で「あれはどういう意味?」「あのパートいる?」という疑問、もしくは「わけのわからなさ」をマイナスに捉えてしまうと、本作の評価は下がってしまうでしょう。
ネタバレなしの前置き2:説明を最小限に「罪を可視化していく」特徴
個人的には「言葉による説明が最小限」「受け手に解釈の余地を残す」「常識では理解し得ない世界に没入できる」作風は大好きなのですが、『鬼滅の刃』のように「全てを説明する」作品を見慣れている人が面食らってしまうのもまた致し方ないかなと。また、後述するように「小説版を読んでやっとわかる部分もある」のは、さすがに不親切にも思えました。
とはいえ、公式サイトの川村元気監督の「あの空間は何か? 異変とは何か?例えばあの空間が人間の心の中で、そこで心に抱いている罪が可視化されていくのだとしたら。そう捉えたら、物語が急に動き出した」という言葉にもある通り、ストーリー性のなかった原作ゲームへ「意味」を持たせる試みは支持したいのです。
余談ですが、「現実の問題を抱えた主人公が変な世界に迷い込む」「大人が子どもを導く(子どももまた大人を導いている)」「起こる出来事が主人公の心理を反映している(罪が裁かれているといえる)」というのは、くしくも同日公開の『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』と共通しています。こちらもぜひご覧になってほしいところです。
『不思議の国でアリスと』就活生が「めちゃくちゃな世界」を冒険する意図とは?
ネタバレなしの前置き3:擬似ワンカット映像は素直にすごい
何より、あの「ループする地下通路」をちゃんと実写映画で、しかも長い長い(擬似)ワンカット映像で成り立たせたことは称賛したいなと。劇場パンフレットの美術担当の杉本亮の言葉によると、(セットは)全長130mの地下通路を2ループ分作られたそうですが、本当に「ずっと続いている」ように見えるんですよね。
また、劇中で何回か「壁のタイルだけを映す」場面があり、おそらくはそこでカットを割っていると思われます。これはアルフレッド・ヒッチコック監督の『ロープ』に通ずる「カット場面で大写しにしてつながっているように見せる」手法でしょう。それでも数分間にわたって本当にワンカットで撮られているのは間違いないですし、時には潔くカットを割ることでメリハリのついた、テンポも削ぎすぎない構成になっていたのも良かったと思います。
さてさて、すっかり前置きが長くなりましたが、ここからはネタバレ全開で、映画『8番出口』の疑問点について解説・考察していきましょう。鑑賞後にお読みください。
※以下より、映画『8番出口』の結末も含むネタバレに触れています。また一部に小説版の記述も含みます。↓
ここからネタバレあり!
疑問1:喘息の設定の意味は?
主人公「迷う男」は喘息持ちで薬の吸引機を常備しています。重要なのは、迷う男が「少年」と出会ってからはほとんど喘息の症状が出ていないこと(後述する強烈な異変「バカンティマウス」を見た直後には咳き込んでいる)でしょう。
喘息の症状そのものは、派遣社員でおそらくは生活も不安定な彼の「生きづらさ」、もしくは不条理な空間に迷い込む彼の「息苦しさ」を示す設定としてちゃんと機能していると思いますし、少年と出会うと症状が少なくなることで「少年を守らないといけない(自身も守ってもらえる)」という「決意」もしくは「父性」を示すことにもなっているとは思うのです。
また、少年も「4番」通路の前で一休みしている際に咳き込んでいるので、少年が迷う男の「未来の息子」であるという伏線にもなっているともいえます。
また、小説版では「数年前に流行した新型のウィルスにかかった」「元々気管が弱かったせいもあり、酷く咳が出た」「結果喘息の症状がこの数年間ずっと続いている」という記述があり、コロナ禍の世相も反映した設定といえます。なお、実際はコロナが喘息の発作のきっかけになっても、コロナは気管支喘息の直接の原因にはならないようです。
参考記事:
疑問2:なぜ少年はしゃべらないのか?
迷う男と出会ったばかりの、「異変ではない」少年がしゃべらないことに違和感を持った方も多いでしょうが、これは後述するように、「その前」に同行していたおじさんこと「歩く男」が声を荒げるタイプの人間のため、「怖かったからしゃべれなかった」というシンプルな解釈が可能でしょう。
また、少年は歩く男が「ニセモノの出口」に行くのを止めようとしたものの、腕を振り払われたために地面に顔をぶつけて頬にケガをしています。そのケガがトラウマになり、だからこそ「その後」に出会う迷う男にもなかなか声をかけられなかった、しかし、しだいに彼を信頼していったからしゃべれるようになった、とも言えるでしょう。
なお、小説版では少年の主観が文章で語られており、彼が幼いながらも真っ当な思考で行動している、その聡明さも伝わるので、彼のことがよくわからなかったという方は読んでみてもいいでしょう。
疑問3:人間の耳・口・目がついたネズミの意味は?
序盤で主人公がXのようなSNSを見た時にもチラッと映っていて、そして終盤に遭遇するのは、「バカンティマウス」と呼ばれる「背中にヒトの耳が生えているかのように見える実験用マウス」です。
1990年代後期のインターネット黎明期、バカンティマウスは「グロ画像」「恐怖画像」として出回っていたそうで、「生きたネズミの背中で軟骨細胞を培養し、背中に人間の耳がついたネズミを創りだした」ことが、倫理的な問題として議論されたのだとか。
異変としては、耳だけでなく「口」「目」もついたネズミも登場します。これはバカンティマウスへ感じる嫌悪感や恐ろしさが「派生した」ものといえるでしょう。
参考記事:
疑問4:「ホームレスの寝床」の意味は?
証明写真機の側に「毛布とコップがある」ことが確認されていましたが、映画ではこれの意味が明かされてはいませんでした。
しかし、小説版では「ホームレスの寝床に誰がいたのか」(ここではその正体は伏せておきます)が書かれており、その彼が「異変は…この通路がお前に見せている罪だ」と明言したりもします。
これは未来も過去もごちゃ混ぜになったような本作の不条理性を示す、または「ループもの」のジャンルとして「おいしい」設定だと思えたので、映画でカットされていたのはちょっと残念でした。
疑問5:「歩く男」ことおじさんのパートの意味は?
物語の視点がおじさんこと「歩く男」へと移るのが、原作ゲームにないサプライズだったわけですが、これが単なる「引き伸ばし」のようなギミックにすぎないという否定的意見も見かけました。
しかし、個人的には歩く男が「人間」として描かれたことにも、ちゃんと意味があると思います。それは、彼が「自分の罪と向き合い苦悩していたものの、結局は自分本位に振る舞ってしまっていた」ことが、ちゃんと少年や自身の罪に向き合おうとした迷う男と対照的な存在になっているから。
小説版での歩く男は「別れた嫁から『せめて子供にはもっと優しくして」と言われた」「今日はその息子に会う日だ」ということも語られる他、彼の主観的な物言いでの「自己正当化」の浅ましさが、その「最後のモノローグ」でより伝わるようになっていました。
疑問6:「歩く女」の女子高生はなぜ極端に低い声になるの?
また、歩く男が出会う「歩く女」こと女子高生が「毎日ぎゅうぎゅう詰めの電車にのって可哀想」というセリフを繰り返し、しだいに低い声になっていくという異変について、小説版での歩く男は「俺の声じゃねえか」と気づいています。女子高生は、自らを憂う歩く男の代弁者なのかもしれません。
また、映画の序盤でYouTuberのヒカキンが、電車に乗り込んでくる役としてカメオ的に出演しています。こちらは話題にするためのおまけ的な演出ではありますが、こうして有名人も「モブ化」する、あるいはループに巻き込まれるかもしれないような感覚も、また面白くあるかなと。
歩く男も(ひょっとすると歩く女も?)、二宮和也が自身をまさに「モブ」として演じたという迷う男も、「どこにでもいる普通の人」で、罪を認めないと、ずっと地下通路を歩く、ループする存在へとなってしまうかもしれない……その恐怖は、繰り返すような日常を部分的にも過ごし、どこかで身近な問題に「見てみぬふり」をする我々にとっても、決して他人事ではないと思うのです。
疑問7:津波の意味は?また未来も過去もごちゃ混ぜの理由
原作ゲームの「地面にスレスレの赤い血(水?)が押し寄せてくる」という、映画『シャイニング』の有名シーンをマイルドにしたような異変は、映画では「瓦礫混じりの濁流と共に押し寄せてくる」という強烈なものに変えられており、公式にも「津波など自然災害を想起させるシーンがございます」とアナウンスされています。
小説版では、迷う男と「ある女」こと恋人の過去において、大震災による大津波で故郷の街が飲み込まれる様をテレビで見ていたこと、それでも「なにもしなかった」ことが語られており、彼が電車で怒鳴られていた赤ん坊とその母親を助けなかったことと同様に、この濁流は大震災があっても故郷を「見捨てた」彼の罪を示していたと言えるでしょう(映画では伝わりにくい部分ですが、冒頭のXのようなSNSでも映ってはいました)。
それでも感動的なのは(物理的に無理があるとも思うのですが)、迷う男が濁流に巻き込まれる中でも、8番出口の看板の上まで少年を持ちあげること。それは美しい波打ち際で自分の息子こと少年と遊んでいた「未来」との対比にもなっています。
なお、この未来が見えているようなシーンついて、小説版では「すべてが並行世界の出来事なのかもしれない」と思いつつも、「だがきっと、それらはすべて関係している」などと結論づけた思想も語られています。大災害である津波、時には穏やかになる「波」という事象を用いて、そのことを端的に示しているとも言えるでしょう。
疑問8:なぜ迷う男は元の場所に戻るのか
ラストで、迷う男は地上へと帰還したわけではなく、電車の中に戻ったというのも象徴的です。考えてみれば、迷う男が少年に向き合ったのは、序盤の事象とは関係のないことで、しかもその少年は未来の息子でもあったという、「身内」へのものなんですよね。そうであれば、この物語が示しているのは、「自分の罪と真に向き合わないと終わらない」問題なのだと。
また、赤ん坊を抱えた女性は、目の前の男性から「満員電車に乗せるなんて常識がねえんだよ!ガキもかわいそうだろ!」と一方的に叫ばれていましたが、小説版では「熱が出たのか、小児科に向かう途中なのだろう」と迷う男から想像されています。
実際の事情はわからないのに、子どもに寄り添う発言をしているようで、結局は自分本位な考えの物言いをするというのは、おじさんこと「歩く男」の少年への言動と一致しています。この思考もまた、他人事ではないでしょう。
もうノイズキャンセリングイヤホンなどで誤魔化さず、赤ん坊を抱えた女性へのところへと向かおうとするラストは、なんてことのない、大したことのない行動なのかもしれませんが、「罪を背負い続けるループ」からの、確かな脱出なのです。

映画ライター。WEB媒体「All About ニュース」「マグミクス」「ねとらぼ」「女子SPA!」「NiEW(ニュー)」、紙媒体「月刊総務」などで記事を執筆中。オールタイムベスト映画は『アイの歌声を聴かせて』。ご依頼・ご連絡はhinataku64_ibook@icloud.comまで。