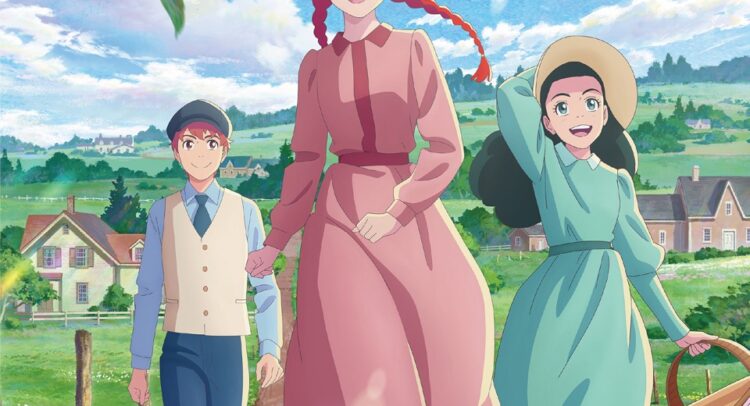ϊ║║ώΨΥήΒψήΒζήΓΓήΒζήΓΓήΔςήΔκήΓνήΓψήΒτίΟ│ήΒΩήΒΕύΦθήΒΞύΚσ
ήΓλήΔ│ήΓ╡ήΔ╝ήΔ╗ήΓ╣ήΓ┐ήΓ╕ήΓςίΙ╢ϊ╜εήΒχήΔΗήΔυήΔΥήΓλήΔΜήΔκήΑΟήΓλήΔ│ήΔ╗ήΓ╖ήΔμήΔ╝ήΔςήΔ╝ήΑΠύυυϊ╕Αϋσ▒ήΑΝϊ╕ΨύΧΝήΒμήΒοήΑΒήΒρήΒοήΓΓήΒΛήΓΓήΒΩήΓΞήΒΕήΒρήΒΥήΒφήΑΞήΓΤϋοΜήΒθήΑΓόευϊ╜εήΒψίΡΞϊ╜εόΨΘίφοήΓΤίΟθϊ╜εήΒτόΝΒήΒκήΑΒόΩξόευήΒτήΒΛήΒΕήΒοήΒζήΒχήΓνήΔκήΔ╝ήΓ╕ήΒψήΑΒί╖ρίΝιώταύΧΣίΜ▓ύδμύζμήΒχ1979ί╣┤ήΒχήΑΟϋ╡νόψδήΒχήΓλήΔ│ήΑΠήΒΝό▒║ίχγήΒξήΒΣήΒθήΓΓήΒχήΒιήΑΓήΒζήΒχίΡΞϊ╜εήΒτίΗΞήΒ│ήΓλήΔΜήΔκήΒπόΝΣήΓΑήΒρήΒΕήΒΗήΒχήΒψήΑΒί░Πό┤ξίχΚϊ║ΝώΔΟήΒχόαιύΦ╗ήΒχήΔςήΔκήΓνήΓψήΓΤόΚΜόΟδήΒΣήΓΜήΓΙήΒΗήΒςήΓΓήΒχήΒπήΒΓήΓΞήΒΗήΑΓ
ήΔςήΔκήΓνήΓψήΒρήΒΕήΒΗήΓΓήΒχήΒψήΒΕήΒνήΒπήΓΓόΠΚήΓΒήΓΜήΑΓίχθίΗβόαιύΦ╗ήΒπήΓΓόΠΚήΓΒήΓΜήΑΓήΔςήΔκήΓνήΓψήΒψίΡΞϊ╜εήΒιήΒΜήΓΚήΔςήΔκήΓνήΓψήΒΧήΓΝήΓΜήΓΠήΒΣήΒπήΑΒήΒΓήΓΚήΒΜήΒαήΓΒόψΦϋ╝ΔήΒΧήΓΝήΓΜώΒΜίΣ╜ήΒτήΒΓήΓΜήΑΓήΒΜήΒνήΒοήΑΒύφΗϋΑΖήΒψήΑΝήΒζήΓΓήΒζήΓΓήΑΒϊ║║ώΨΥήΒψήΔςήΔκήΓνήΓψήΒτίΟ│ήΒΩήΒΕύΦθήΒΞύΚσήΒπήΒΓήΓΜήΑΞήΒρόδ╕ήΒΕήΒθήΒΥήΒρήΒΝήΒΓήΓΜήΑΓ
ήΔςήΔκήΓνήΓψήΓλήΔΜήΔκήΒψήΒςήΒεόΚ╣ίΙνήΒΧήΓΝήΓΜήΒχήΒΜήΑΑήΔκήΔΘήΓμήΓλώΨΥέΑεύ┐╗όκΙέΑζήΒχόφ┤ίΠ▓ήΒΜήΓΚήΒ┐ήΓΜήΔςήΔκήΓνήΓψήΒχίΚ╡ώΑιόΑπΎ╜εReal SoundΎ╜εήΔςήΓλήΔτήΓ╡ήΓοήΔ│ήΔΚ όαιύΦ╗ώΔρ
όαιύΦ╗όΚ╣ϋσΧίχ╢ήΒχίΝΩόζΣίΝκί╣│ό░ΠήΒψήΔςήΔκήΓνήΓψόαιύΦ╗ήΒρήΒψήΑΒήΑΝήΔςήΔκήΓνήΓψόαιύΦ╗ήΑΞήΒψήΑΝήΓςήΔςήΓ╕ήΔΛήΔτόαιύΦ╗ήΒρήΒχόψΦϋ╝ΔήΑΞήΒρήΒΕήΒΗίχ┐ίΣ╜ήΓΤϋΔΝϋ▓ιήΒμήΒοϊ╕ΨύΧΝήΒτύΦμήΒ┐ϋΡ╜ήΒρήΒΧήΓΝήΑΒήΑΝύΕ╝ήΒΞύδ┤ήΒΩήΑΞήΓΕήΑΝίΚ╡ώΑιίΛδήΒχόυιίοΓήΑΞήΒρήΒΕήΒΗίδ║ίχγϋο│ί┐╡ήΒΜήΓΚώταήΒΠϋσΧϊ╛κήΒΧήΓΝήΓΜήΒΥήΒρήΒψήΒΓήΒ╛ήΓΛήΒςήΒΕήΑΓήΑΝίΧΗόξφύγΕήΒτήΔςήΓ╣ήΓψήΔαήΔΔήΓ╕ήΑΞήΒπήΒΞήΓΜήΔκήΔςήΔΔήΔΙήΒΝήΒΓήΓΜϊ╕ΑόΨ╣ήΒπήΑΒήΑΝϋΛ╕ϋκΥϊ╜είΥΒήΒρήΒΩήΒοήΒψήΔςήΓ╣ήΓψήΓΤϋ▓ιήΒμήΒοήΑΞήΒΕήΓΜήΒρϋςυόαΟήΒΩήΒοήΒΕήΓΜήΒχήΒιήΒΝήΑΒίΖρήΒΠίΡΝόΕθήΒπήΒΓήΓΜήΑΓΎ╝ΙήΑΟήΔςήΔκήΓνήΓψόαιύΦ╗ήΒχίΚ╡ώΑιίΛδήΑΠό░┤ίμ░ύν╛ήΑΒ2017ί╣┤ήΑΒύ╖ρϋΣΩΎ╝γίΝΩόζΣίΝκί╣│ήΔ╗ί┐ΩόζΣϊ╕Κϊ╗μίφΡήΑΒP16Ύ╝Κ
ήΔςήΔκήΓνήΓψήΓΤϋσΧήΒβήΓΜόβΓήΑΒίΑΜϊ║║ύγΕήΒτό░ΩήΓΤήΒνήΒΣήΒοήΒΕήΓΜήΒχήΒψόψΦϋ╝ΔίΕςίΛμήΒχύβ║όΔ│ήΒτώβξήΓΚήΒςήΒΕήΓΙήΒΗήΒτήΒβήΓΜήΒΥήΒρήΒιήΑΓόψΦϋ╝ΔήΒπήΒψήΒςήΒΠήΑΒόΨ╣ίΡΣόΑπήΒχώΒΧήΒΕήΑΒόβΓϊ╗μύ▓╛ύξηήΒχίΙ╗ίΞ░ήΒχήΒΧήΓΝόΨ╣ήΒςήΒσήΑΒίΕςίΛμήΒχϊ╕Λϊ╕ΜώΨλϊ┐ΓήΒπόΞΚήΒΙήΓΜήΒχήΒπήΒψήΒςήΒΠήΑΒό░┤ί╣│ήΒτήΑΝύΧ░ήΒςήΓΛόΨ╣ήΑΞήΓΤϋοΜήΓΜήΑΓήΒΥήΓΝήΒΝήΒπήΒΞήΒςήΒΕήΒρήΔςήΔκήΓνήΓψήΓΓήΒχήΓΤϋοΜήΓΜήΒθήΓΒήΒχήΓ╣ήΓ┐ήΔ╝ήΔΙίε░ύΓ╣ήΒτύτΜήΒοήΒςήΒΕήΒρόΑζήΒμήΒοήΒΕήΓΜήΑΓ
ήΑΑ
όκεήΒχϋΛ▒ήΒ│ήΓΚήΓΤόΟ┤ήΒ┐ήΒτήΒΕήΒΠήΓλήΔ│ήΔ╗ήΓ╖ήΔμήΔ╝ήΔςήΔ╝
ήΒΧήΒοήΑΒήΓλήΔ│ήΓ╡ήΔ╝ήΔ╗ήΓ╣ήΓ┐ήΓ╕ήΓςήΒχήΑΟήΓλήΔ│ήΔ╗ήΓ╖ήΔμήΔ╝ήΔςήΔ╝ήΑΠήΒψήΑΒήΒσήΒΗήΒΕήΒΗόΨ╣ίΡΣόΑπήΓΤόΚΥήΒκίΘ║ήΒΩήΒοήΒΕήΓΜήΒχήΒΜήΑΓ
1ϋσ▒ήΒιήΒΣήΒπϋςηήΓΝήΓΜήΒΥήΒρήΒψήΒΧήΒ╗ήΒσίνγήΒΠήΒςήΒΕήΒΩήΑΒύ╡ΡϋτΨήΓΤόΑξήΒΟήΒβήΒΟήΓΜήΒχήΒψϋΚψήΒΠήΒςήΒΕήΑΓήΒιήΒΝήΑΒϊ╕╗ϊ║║ίΖυήΓλήΔ│ήΒχήΓφήΔμήΔσήΓψήΓ┐ήΔ╝ϊ╗αήΒΣήΒτήΒνήΒΕήΒοήΒψώταύΧΣύδμύζμϊ╜είΥΒήΒρήΒψύ╡ΡόπΜώΒΧήΒΗήΑΓύτψύγΕήΒτήΒΜήΒςήΓΛί┐τό┤╗ήΒςίΖΔό░ΩήΒΕήΒμήΒ▒ήΒΕήΒχίξ│ήΒχίφΡήΒρήΒΩήΒοόΠΠήΒΕήΒοήΒΕήΓΜήΑΓήΒρήΓΓήΒβήΓΝήΒ░ήΑΒϋΡ╜ήΒκύζΑήΒΞήΒχήΒςήΒΕήΒΠήΓΚήΒΕίΖΔό░ΩήΒςίφΡήΒιήΑΓ
ώταύΧΣύΚΙήΒχήΓλήΔ│ήΒψήΑΒόΔ│ίΔΠίΛδϋ▒ΛήΒΜήΒπήΒΛήΒΩήΓΔήΒ╣ήΓΛήΒςώΔρίΙΗήΒψίΖ▒ώΑγήΒβήΓΜήΒΝήΑΒήΓΓήΒμήΒρϋΡ╜ήΒκύζΑήΒΕήΒθώδ░ίδ▓ό░ΩήΒχίξ│ήΒχίφΡήΒιήΒμήΒθήΑΓήΒΥήΒΥήΒτήΒψόβΓϊ╗μύ▓╛ύξηήΒχώΒΧήΒΕήΒΝόαΟύλ║ήΒτϋκρήΓΝήΒοήΒΕήΓΜήΒρήΒψόΑζήΒΗήΑΓύΠ╛ϊ╗μήΒψήΒβήΒπήΒτήΑΝίξ│ήΒχίφΡήΒψήΒΛήΒΩήΒρήΓΕήΒΜήΒπήΒΓήΓΜήΒ╣ήΒΞήΑΞήΒρήΒΕήΒΗύ▓╛ύξηόΑπήΒπήΒψήΒςήΒΕήΑΓ
ώπΖήΒπήΔηήΓ╖ήΔξήΓοήΒρήΒχίΙζίψ╛ώζλήΒπί░Πϋ╡░ήΓΛήΒπώπΗήΒΣίψΕήΒμήΒοήΒΕήΒΠήΓλήΔ│ήΑΒήΓ░ήΓνήΓ░ήΓνήΒρήΔηήΓ╖ήΔξήΓοήΒτϋ┐ΣήΒξήΒΕήΒοΎ╝Ιώφγύε╝ήΔυήΔ│ήΓ║ήΓΤϊ╜┐ύΦρήΒΩήΒοήΒΕήΓΜήΓτήΔΔήΔΙΎ╝ΚήΔηήΓ╖ήΔ│ήΓυήΔ│ήΒχήΓΙήΒΗήΒτίΨΜήΓΛίΑΤήΒβήΓλήΔ│ήΑΒώουϋ╗ΛήΒτίΨεήΒ│ίΜΘήΓΥήΒπώμδήΒ│ϋ╖│ήΒφήΒςήΒΝήΓΚώπΗήΒΣήΒοήΒΕήΒΠήΓλήΔ│ήΑΒίΖΔό░ΩήΒΕήΒμήΒ▒ήΒΕήΒςόΠΠίΗβήΒιήΑΓ
όβΓϊ╗μήΓΤίνΚήΒΙήΒοήΔςήΔκήΓνήΓψήΒΧήΓΝήΓΜήΒΥήΒρήΒχώΗΞώΗΡίΣ│ήΒχϊ╕ΑήΒνήΒψΎ╝ΙόΚ╣ίΙνήΓΤίΠΩήΒΣήΓΜήΔζήΓνήΔ│ήΔΙήΒπήΓΓήΒΓήΓΜήΒΝΎ╝ΚήΑΒόβΓϊ╗μύ▓╛ύξηήΒΝήΒσήΒΗίΠΞόαιήΒΧήΓΝήΒοήΒΕήΓΜήΒΜήΓΤϋοΜήΒνήΒΣήΓΜήΒΥήΒρήΑΓήΒΜήΒνήΒοήΒχϊ╛κίΑνϋο│ήΒπύ╖ρήΒ╛ήΓΝήΒθύΚσϋςηήΓΤίΙξήΒχϊ╛κίΑνϋο│ήΓΤί░ΟίΖξήΒΩήΒθόβΓήΑΒήΒσήΒΗήΒΕήΒΗίΝΨίφοίΠΞί┐εήΒΝίΘ║ήΓΜήΒχήΒΜήΑΒήΒζήΓΝήΒψήΒσήΓΥήΒςίΣ│ήΒςήΒχήΒΜήΓΤϋοΜήΒνήΓΒήΓΜήΒΥήΒρήΒπήΑΒϋοΜήΒΙήΒοήΒΠήΓΜήΓΓήΒχήΓΓήΒΓήΓΜήΑΓ
ήΔηήΓ╖ήΔξήΓοήΒρώουϋ╗ΛήΒτϊ╣ΩήΒμήΒοήΒΕήΓΜώΒΥϊ╕φήΑΒήΓ╡ήΓψήΔσήΒχόΧμήΓΜϋΛ▒ήΒ│ήΓΚήΓΤύδχϊ╕ΑόζψόΚΜήΓΤϊ╝╕ήΒ░ήΒΩήΒοόΟ┤ήΓΓήΒΗήΒρήΒβήΓΜήΓλήΔ│ήΒψήΑΒϋΔ╜ίΜΧύγΕήΒτϊ╜ΧήΒΜήΓΤόΟ┤ήΒ┐ίΠΨήΓΜήΑΒήΓλήΓψήΔΗήΓμήΔΨήΒςίξ│ήΒχίφΡήΒςήΒχήΒιήΑΓήΒΩήΒΜήΓΓήΑΒϋΛ▒ήΒ│ήΓΚήΓΤ3όηγήΒΠήΓΚήΒΕόΟ┤ήΓΥήΒπήΒΕήΓΜήΑΓήΒΥήΒχϋΘςήΓΚήΒνήΒΜήΒ┐ήΒτϋκΝήΒΠϋΔ╜ίΜΧόΑπήΒΝϊ╗ΛίδηήΒχήΑΟήΓλήΔ│ήΔ╗ήΓ╖ήΔμήΔ╝ήΔςήΔ╝ήΑΠήΒχύΚ╣ί╛┤ήΒπήΒψήΒςήΒΕήΒΜήΑΓ
ήΒΥήΒχήΓ╖ήΔ╝ήΔ│ήΑΒώταύΧΣύΚΙήΒπήΒψϊ╕κόΚΜήΓΤϋ║τϊ╜ΥήΒχίΚΞήΒπύ╡ΕήΓΥήΒπήΑΒϋοΜήΒρήΓΝήΒςήΒΝήΓΚύσ║όΔ│ήΒτήΒ╡ήΒΣήΓΜήΒρήΒΕήΒΗόΠΠίΗβήΒπίΠΩίΜΧύγΕήΒρήΒΕήΒΙήΒ░ίΠΩίΜΧύγΕήΒιήΑΓήΒιήΒΜήΓΚόΓςήΒΕήΒρήΒΕήΒΗήΒΥήΒρήΒπήΒψήΒςήΒΠήΑΒόβΓϊ╗μύ▓╛ύξηήΒχϋκρήΓΝόΨ╣ήΒχώΒΧήΒΕήΒιήΑΓ
ήΒσήΒμήΒκήΓΓόΔ│ίΔΠίΛδήΒχίΕςήΓΝήΒθίξ│ήΒχίφΡήΒρήΒΕήΒΗύΓ╣ήΒπήΒψήΑΒήΓλήΔ│ήΒχόευϋ│ςήΓΤίνΨήΒβήΓΓήΒχήΒπήΒψήΒςήΒΕήΒρϊ╗ΛήΒχήΒρήΒΥήΓΞήΒψόΑζήΒΗήΑΓ
ήΒΓήΒρήΑΒύυυϊ╕Αϋσ▒ήΒχύ╡╡ήΓ│ήΔ│ήΔΗήΒτώΨλήΒΩήΒοήΒψήΑΒήΓψήΔφήΔ╝ήΓ║ήΓλήΔΔήΔΩήΒΝίνγήΒΕήΒςήΒρόΑζήΒμήΒθήΑΓύσ║ώΨΥήΓΤήΓΓήΒΗί░ΣήΒΩόξ╜ήΒΩήΒ┐ήΒθήΒΕήΒρήΒΕήΒΗό░ΩόΝΒήΒκήΓΓήΒΓήΓΜήΒΣήΒσήΑΒόβχώΑγήΒτύυυϊ╕Αϋσ▒ήΒψόξ╜ήΒΩήΓΥήΒιήΑΓ
ήΑΑ
ήΒκήΒςήΒ┐ήΒτήΔηήΔ╝ήΔΗήΓμήΔ│ήΔ╗ήΓ╖ήΔ╝ήΔ│ήΒΝήΔηήΓ╖ήΔξήΓοί╜╣ήΒχίχθίΗβόαιύΦ╗ύΚΙήΓΤϋοΜήΒθήΒΥήΒρήΒΓήΓΜήΒΝήΑΒϋΚψήΒΕήΔφήΓ▒ήΔ╝ήΓ╖ήΔπήΔ│ήΒπόΤχί╜▒ήΒΩήΒοήΒΕήΒοώλρόβψήΒΝϋοΜί┐εήΒΙήΒΝήΒΓήΓΜήΑΓήΒΩήΒΜήΒΩήΑΒόκεήΒψήΒςήΒΕήΒχήΒΝόΩξόευϊ║║ήΒρήΒΩήΒοήΒψίψΓήΒΩήΒΕήΓΥήΒιήΓΙήΒφήΑΓίδ╜ήΒΝώΒΧήΒΙήΒ░ώλρόβψήΒτίψ╛ήΒβήΓΜόΕθίΠΩόΑπήΓΓώΒΧήΒΗήΒΩήΑΒήΓτήΔΛήΔΑήΒψόκεήΒΝϊ╕ΑϋΙυύγΕήΒαήΓΔήΒςήΒΕήΒιήΓΞήΒΗήΒΩήΑΓ
┬σΎ╕ΟήΓλήΔ│ήΔ╗ήΓ╖ήΔμήΔ╝ήΔςήΔ╝ϋμ╜ϊ╜είπΦίΥκϊ╝γ