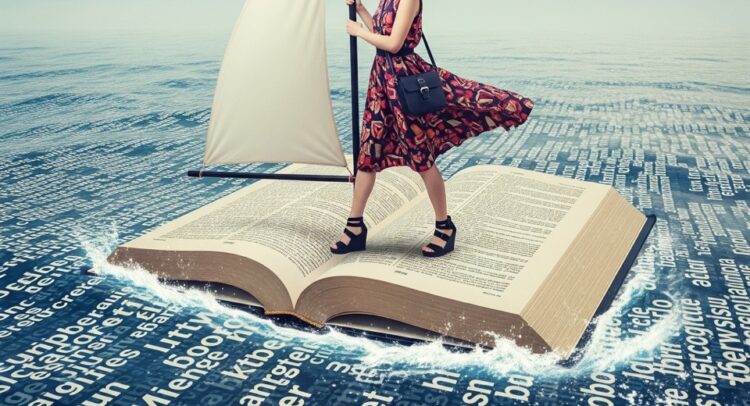三浦しおんによる小説『舟を編む』は、単なるベストセラーにとどまらない現代日本文学の一つの現象だ。広大で深遠な「言葉の海」を渡るための「舟」=辞書を編む人々の物語は、2012年の本屋大賞受賞を皮切りに、映画、アニメ、そして2024年のNHKBSドラマ『舟を編む 〜私、辞書つくります〜』へと、メディアの形を変えながら多くの人々の心を捉え続けてきた。そのNHKドラマ版が地上波で放送開始された。
池田エライザを新たな主人公に迎えた本作は、これまでの作品とは異なる航路を取りながらも、物語の核心にある「言葉の力」と「物作りの魂」を見事に描き出している。本稿では、ドラマ版の魅力を軸に、歴代作品との比較を通して、この不朽の物語が現代に放つ新たな光を分析する。
目次
ファッション誌から辞書作りへ―池田エライザ演じる主人公の戸惑い
物語は、岸辺みどり(池田エライザ)が海辺で慟哭する印象的なシーンから幕を開ける。ファッション誌『VIVIAN』の編集者として働く彼女は、同僚との会話で意味の異なる「やばい」を連発するなど、現代の若者像を体現した人物だ。しかし、雑誌業界の不振により、自身が編集していた雑誌は廃刊。みどりは会社から「ビッグプロジェクトへの大抜擢」を告げられる。
期待に胸を膨らませた彼女が異動したのは、社内の古びた一角にある「辞書編集部」。そこは、膨大な資料と「用例採集カード」に埋もれ、主任の馬締光也(野田洋次郎)をはじめ、ごく少人数のスタッフが黙々と作業をする、華やかなファッション業界とは全く異なる世界であった。「大抜擢」という言葉とは裏腹の現実に、みどりは騙されたのではないかと先行きに強い不安を覚える。ファッションという目に見える「モノ」を扱っていた彼女が、目に見えない「言葉」を扱う世界へと足を踏み入れた瞬間の戸惑いは、多くの視聴者が共感する物語の巧みな入り口となっている。
原作、映画、アニメとどう違うのか?―2024年ドラマ版の新たな『舟』
『舟を編む』の映像化は今回が初めてではない。2013年の映画版は松田龍平が演じる馬締光也の静かな情熱と成長に焦点を当てて日本アカデミー賞を席巻し、2016年のアニメ版は連続形式を活かして辞書編纂のプロセスと編集部全体の群像劇を丁寧に描いた。これらの作品では、対人関係は不器用だが言語への鋭い感覚を持つ馬締が、常に物語の中心にいた。
しかし、2024年のドラマ版は最も大胆な再解釈を試みる。主人公を、ファッション誌から異動してきた岸辺みどりに変更したのだ。これは、物語の魂を現代の観客に届けるための、見事な「再翻訳」と言える。当初、辞書を「言葉と説明だけ」と見ていた部外者のみどりを主人公に据えることで、紙の辞書に馴染みのない視聴者をも、彼女と共に言葉の魔法を発見する旅へと自然に誘う。
この変更により、野田洋次郎が演じる馬締光也は、主人公ではなく「風変わりでミステリアスな指導者」という新たな役割を担う。歴代の馬締像とは異なる立ち位置から、みどりの才能を見出し、辞書作りの世界へといざなう。池田エライザ演じるみどりの視点を通して、私たちは辞書編集部という未知の世界と、馬締という特異な人物を新鮮な驚きをもって体験することになる。これは単なるリメイクではない。物語の核となるテーマの普遍性を信じ、その魂を現代に生かし続けるための、意欲的な「再創造」といえるだろう。見事な翻案だ。
「右」を言葉で説明できるか?―『舟を編む』が問う言葉の力
「右を言葉で説明するとしたらどうしますか?」。歓迎会で馬締にそう問われたみどりは、思わず矢印を書いてしまう。この「右」の定義の難しさは、原作から続くシリーズ共通のモチーフであり、直感的な理解と言語による表現の間の溝を浮き彫りにする。
本作は、このテーマをさらに深掘りする。「この世に悪い言葉は存在しない。悪いのは言葉の選び方を間違えた人」という監修者・松本朋佑(柴田恭兵)の言葉は、作品の核心を貫く。言葉の力は、その定義の中にだけあるのではない。それがどのように使われるかにかかっている。みどりは、国語が苦手で辞書も持っていないと自嘲するが、彼女の本当の課題は知識の有無ではない。無意識に使った言葉が意図せず相手を傷つけたり、見下していると受け取られたりすること――まさに「言葉の使い方」こそが、彼女の根源的な悩みなのである。
物語は、辞書が「歪みの少ない鏡」であるという思想も描き出す。ドラマの終盤、みどりは何気なく使っていた「なんて」という言葉を辞書で引く。そこに記された「軽視」の意味を知り、自らの言葉の無自覚さに気づき、衝撃を受ける。この瞬間、辞書は彼女にとって単なる物の羅列ではなく、自分自身を映し出す鏡となった。言葉のプロである馬締が恋文に苦心したように、言葉を知っていることと、それを使って誰かと心を通わせることは全く別の問題である。みどりの成長物語は、言葉を知り、その使い方を学び、他者と、そして自分自身と、より良い関係を築いていく旅路そのものなのだ。その海を渡る旅路のための船が辞書なのだ。
新時代に向けて編み始めた舟
『舟を編む』という物語は、小説が築いた深遠な主題的基盤の上で、映画はその感情的な核心を詩的に昇華させ、アニメは緻密な世界観を探求した。そして2024年のドラマ版は、主人公を現代的な視点を持つ女性に据えることで、この物語を全く新しい世代に向けて見事に再創造した。
池田エライザ演じる岸辺みどりと共に、私たちは辞書作りという静かで埃っぽい世界が、いかにスリリングで感動的な人間ドラマであるかを再発見する。それは、丹念な職人技の重要性と、そして何よりも、他者と繋がるために正しい言葉を探し求めるという、人間の根源的で終わりなき探求の尊さを教えてくれる。『大渡海』を渡る旅は、美しくも困難な、無限の言葉の海を渡る我々自身の旅路と重なる。ドラマ『舟を編む』は、まさに「今」という時代に最も響く、見事な舟を編み始めたと言えるだろう。
登場人物
岸辺みどり(池田 エライザ)
馬締光也(野田 洋次郎)
宮本慎一郎(矢本 悠馬)
林香具矢(美村 里江)
佐々木薫(渡辺 真起子)
天童充(前田 旺志郎)
荒木公平(岩松 了)
西岡正志(向井 理)
松本朋佑(ともすけ)(柴田 恭兵)