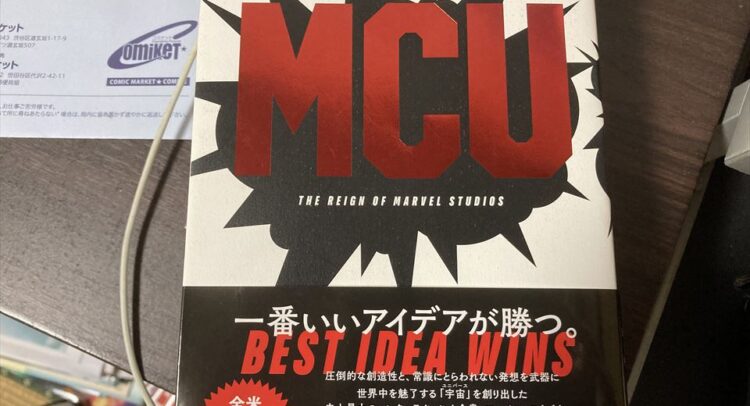フィルムアート社から刊行された『MCU 比類なき映画スタジオの驚異的〔マーベル〕な逆転物語』は、IPビジネスに興味ある人はぜひ読んでおくべき一冊だ。
編集部から献本いただいたので早速読ませていただいた。585ページの分厚い内容で、『アイアンマン』の1作目が製作される前(フェイズ0)からマルチバース展開が本格化するフェイズ4までの、制作とビジネスの舞台裏を関係者の証言と膨大な資料をもとに紐解いた本だ。
この本は、マーベル世界の考察本ではないし、作家たちのクリエイティビティにスポットを当てた本ではない。監督や俳優たちは多数登場するが、どちらかというと中心となるのは、マーベル・スタジオ創設者のアヴィ・アラッドや90年代にマーベルを買収したトイ・ビズ社のアイク・パルムッター、マーベル・スタジオの元COOデヴィッド・メイゼルや、ディズニーCEOのボブ・アイガーにボブ・チャペック、そしてケビン・ファイギだ。
MCUは、30年かけて世界のIPビジネスの覇権的存在と言えるまでに成長した。その成長の裏側には、様々な思惑を持った人物たちの利益相反やガチガチの契約書があり、クリエイティビティとビジネスの綱引きがあり、偏見と多様性の戦いがあった。それらの絶え間ない「調整」によってMCUはIPビジネスの頂点に君臨したのだというのがよくわかる内容だ。
そういう意味では、マーベル作品に興味がなくても、エンタメビジネスに関心ある人なら必ず楽しめるし、参考になる話ばかりだ。
本書はマーベルをヨイショする姿勢で書かれていない。プロローグにこうある。
本書の執筆を始めた頃、マーベル・スタジオからの妨害はなかった。少なくとも最初の数ヶ月は。しかしやがて、ディズニーが関係者に、私たち執筆者と会って話をするなと伝えているという噂を聞くようになった。(P21)
執筆にさいして、色々な戦いがあったことが察せられるが、少なくとも太鼓持ちが書いた内容ではないということは確かだろう、
マーベル・スタジオ(LA)とマーベル・エンターテインメント(NY)の熾烈な戦い
本書は、マーベルが苦境にあえいでいた1990年代から始まる。破産やトイビズの買収を経て、組織再編、そこからキャラクターの映画化権を切り売りしていた中で、フォックスが『X-MEN』を、ソニーが『スパイダーマン』を成功させる。だが、マーベルに入る利益が薄いので、自らが映画製作に乗り出し、パラマウントと配給契約を結ぶ。ここに至るまでの顛末が事細かに記され、皆が知っている(あるいはそんな作品もあったなと忘れている)作品群が言及されていく。
そして、MCU一作目が『アイアンマン』に決まった理由は、「役員たちは、いい玩具になると知っていた」からだった。2005年の市場調査でそういう結果があったのだそうだ。(P81)。
この「玩具の売り上げ」というファクターは、一作目のみならず、もっと後になってもずっとMCUの企画決定に際して大きな影響力を持っていたことが本書を読むとよくわかる。あれだけ、映画をヒット連発させて栄華を極めているように見えても、おもちゃの売り上げポテンシャルで企画にGOが出るかどうかが決まっていたのだ。
このおもちゃの売り上げを気にするのは、NYに本社を構えるアイク・パルムッター率いるマーベル・エンターテインメントで、映画製作を主導するのは、LAにスタジオを構えるマーベル・スタジオだった。この2つの対立が本書のポイントとなっている。
『アベンジャーズ』一作目に登場するヒーローを決める際、パルムッターの関心はアベンジャーズのメンバーが全員男性であるかどうかだったと本書には書かれている。
パルムッターは自分の商売をよく理解していた。パルムッターの商売に大事なのはマーベルより玩具だった。女性キャラクターのアクション・フィギュアは売れない、女性が主役のコミックスは男性が主役のものより売れない、そして女性のスーパーヒーローが主役の映画は興行成績が悪かったという持説を正当化するために、パルムッターは都合よく選別したデータを載せた予算書をひけらかした。しかし、ウェドンは、アベンジャーズには女性が最低でも1人、願わくばブラック・ウィドウが参加しなければ駄目だと言い張った。
ファイギはウェドンの味方をした。ラファロによると、ファイギは「皆、聞いてくれ。明日には僕はここにいないかもしれない。誰も女性のスーパーヒーローが主役の映画を観に来ないとアイクは信じている。だから、僕が明日もまだここにいたら、僕が勝ったということだなんだ」。ファイギは解雇されず、ブラック・ウィドウはアベンジャーズのメンバーになった。(P229)
このような対立の緊張関係の中、MCUというIPは大きくなっていったのだ。
「玩具の売り上げが企画を左右する」というのは、例えば日本のロボットアニメにも共通している部分があるかもしれない。スポンサーの要求にどう応えて、自分たちのクリエイティブを発揮するのか。本書には、そんな絶え間ない「調整」の努力がたくさん書かれている。
ケビン・ファイギのプロデュース能力の高さ
上で引用した箇所でも分かる通り、MCUを引き締めているのは、やはりケビン・ファイギだ。本書を通して、彼のプロジェクトをハンドリングする能力の高さがやはり目につく。実質マーベル映画の監督はケビン・ファイギであって、その上で各作品の監督たちが個性を振るうという形になっている。MCUは単独の映画ではなく、それぞれがつながる「シリーズ」なのだとすれば、ケビン・ファイギは超優秀なショーランナーのようなものだろう。
そんなケビンがマーベルに関わり出したのは、フォックスの『X-MEN』からだ。意外にも彼はすごい熱心なマーベルファンというわけではなかったらしい。最初は登場するミュータントにも詳しくなかったが、『X-MEN』の撮影に参加することになると、「瞬く間にその道のエキスパート」になり、現場で「歩くマーベル辞典」と目されるようになったらしい(P59)。
そういうところから始めて、マーベル・スタジオの責任者となり、パルムッターとの戦いを経て、ディズニーの後ろ盾を得てパルムッター以上の権力を手中に収めていく。本書はMCUの内幕を書いた内容だが、同時にケビン・ファイギという一人の男の立身出世の物語としても読める。
IPビジネスは絶え間ない調整の連続
本書は、集団作業のクリエイティビティとビジネスとはどういうものかを赤裸々に見せてくれる。各所の利害、それは玩具の売り上げだったり、映画公開日の調整だったり、中国という急成長する巨大市場への目くばせだったり、高騰し続ける俳優へのギャラの捻出だったり、スターが脚本に注文できる権利だったり、色々だ。それらを適宜調整しながら、MCUはIPを発展させてきた。
MCUはそれぞれの作品が絡み合うように展開しているから、きちんとつじつまが合うように、大きなロードマップを作ってそれに従って展開しているのかと思いきや、そんなスムーズなものでは全然なかったというのがよくわかる。撮影直前になっても、脚本が出来ておらず、役者たちがどんな役をえんじるのかわからない状態も珍しくなく、脚本も多くの人が関わり改稿するため、脚本組合の調停をしょっちゅう受けている。
VFX部門はさらに大変だ。「なんでもできます課(Department of YES)(P450)と皮肉を込めて呼ばれるVFX部門にかかる比重が、年を追うごとに増していく様子が書かれている。VFXのショット量がどんどん膨大になっていき予算も膨れがっていく上に、作品数も増えていく。
マーベル作品のVFX部門の長時間労働や待遇の悪さが取りざたされたことがあったが、本書はそうなってしまう仕組みをこう語る。
恐らくマーベルは一番見積もりが安い工房を選ぶので、仕事が欲しければどれだけ利ざやを削れるかの勝負になる。入札が終わってしばらくすると、マーベル・スタジオは同程度の見積もりを期待しながら他のプロダクションの入札を始める。もちろん小さな特殊効果のスタッフたちが、自分たちが働く会社が倒産しないように週末返上で長時間働いてくれることなどお構いなしだ。(P463)
本書はマーベルの達成した功績に触れつつ、こうした負の側面にもスポットを当てる。ディズニーが執筆陣を警戒して接触を禁止したとしても不思議ではないような内容だ。
今もMCUは、ジョナサン・メジャースの不祥事によって大掛かりなプラン変更を余儀なくされ、ロバート・ダウニー・Jr.の復帰によってそれを乗り切ろうとしている。その試みが上手くいくのかわからない、そして「スーパーヒーロー疲れ」という言葉も出てくるようになっていて、スーパーヒーロー映画ジャンル自体の勢いに疑問符が投げかけられてもいる。
しかし、マーベルはこれまでも数多くのトラブルを乗り越えてきているというのが、本書を読むと分かる。この苦難を切り抜けてきたマーベルは、多少の逆風が吹いてもそう簡単には崩れないだろうという気がしてくる。数々のピンチをチャンスに変えて、現在のIP帝国を築いてきたマーベルは今も虎視眈々と抜け目なく有効な一手を考えているのかなという気がしてくる。
IPビジネスは一筋縄ではいかないものだと、よくわかる内容だ。エンタメビジネスに関心ある人はぜひ読んでほしい。