2011年、9.11の首謀者とされるオサマ・ビン・ラディンを米軍が殺害したとの報が流れた時、アメリカでは確かにそれを歓迎するようなムードがあった。僕のフェイスブックの友人にも正義は貫徹されたと書き込むテキサス出身の白人もいれば、ビン・ラディン殺害の後になされたオバマ大統領のスピーチに心から拍手すると書いていたインド出身の女の子など、様々な反応があった。その時、すでに僕はアメリカから日本に帰国していたので、その空気を現地で感じるきかいはなかったのだが、フェイスブックを通じて微かにそれは伝わってきた。確かにオサマ・ビン・ラディンの殺害は、21世紀のアメリカにとって一大ビッグイベントだったろう。
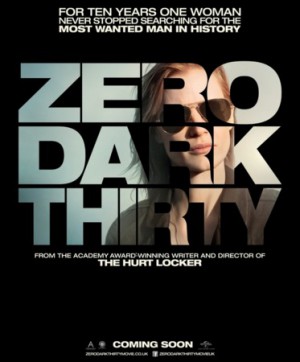
ハート・ロッカーとグリーン・ゾーン
キャスリン・ビグロー監督はオスカー作品賞を受賞した『ハート・ロッカー』でイラク戦争を題材にした作品を撮っている。ほぼ全編イラクを舞台にした作品であるが(撮影は米国内)、徹底的にアメリカの国内問題を描いていた。イラクという周りはみな敵だらけでどこから狙われているのか、どこに爆弾が仕掛けられているかわからない場所で、大義のない戦争に参加した兵士たちの苦悩を通じて当時のアメリカ社会の抱えていた問題意識をとてもリアルに描いていた。当時僕はアメリカに住んでいたので、その空気をリアルに体感できた。
しかし、ハート・ロッカーはイラクを舞台にしておきながら、アメリカの国内問題だけを描いた作品だった。そこにアメリカ以外の外部の視点はない。アメリカ自身の反省は描くが、もう一人の当事国であるはずのイラクについては描いていない。
ハート・ロッカーと同時期にイギリス人監督のポール・グリーンダラスが『グリーン・ゾーン』という作品がある。この作品もイラクを舞台にした大量破壊兵器を巡るいざこざを描いていて、やはりアメリカの国内問題なのだが、最後にマット・デイモン扮する主人公にずっと協力していたイラク人、フレディの「裏切り」により、そうした国内的な視点しか持たないアメリカの姿勢そのものを批判する作品になっていた。この映画をハート・ロッカーと同じくアメリカ的な自己中心的な世界観に基づいて作られたと評するのは謝り。むしろ一流の娯楽作品として展開させておいて、その後のどんでん返しでアメリカ批判を、外部の視点からしてみせた作品だった。
アメリカの21世紀の恥部を描く作品
アメリカの21世紀は9.11とともに始まったと言っていい。ビン・ラディンの仕掛けた一発のテロが10年間のアメリカの外交を決定づけたと過言ではない。そのビン・ラディン殺害までの過程、捜査の中心にいた人物を主人公とした本作「ゼロ・ダーク・サーティ」は、やはりハート・ロッカーの時を同様の視座で製作されているように思う。2001年から2011年までのアメリカの苦悩、醜さ、執念、憎悪を存分にあぶり出している。
決してアメリカは正義だ、などと声高に叫ぶ映画ではない。むしろ前半は目的のためなら拷問を辞さず、というアメリカの醜悪さを描いているし、世論が拷問や虐待に冷たい視線を向けることに苛立ちすら感じている登場人物たちを決して共感可能に描いてはいない。
ストーリーは、ビン・ラディンの在処を突き止めるためにの情報戦や同僚、上司との衝突を中心に展開し、サスペンス映画としての要素が強い。ビン・ラディンの連絡係を突き止める際の捜査線、突入の際の緊張感はまさに手に汗にぎる、目を釘付けにする力強さがある。
しかし、この映画、作劇の基本から逸脱したような欠点がある。今日本に住んでいる僕からすると欠点に見えるが、もしかしたらアメリカ人にとっては欠点と思わないような欠点が。
描かれない主人公の動機
作劇の基本は、物語全体の主人公の目標を提示し、なぜ彼/彼女がそれを追い求めるのか動機を描くのが基本。いちいち例を挙げなくてもドラマでもアニメでも見た事のある人ならわかるはず。目標となぜそれに向かうのかの動機がわからなければ、人物に感情移入もできないし、ハラハラドキドキもしようがない。
しかし、この映画にはそれがない。主人公のマヤは映画の始まりのシーンでもうこのビン・ラディンの捜査チームに巻き込まれている。その後もなぜ彼女はあれほどの執念でビン・ラディンを追いかけるのか、ほとんど説明がない。映画の中ごろに同僚を自爆テロで殺され、「復讐」という動機が芽生えたようだが、その前から彼女は相当の執念を持って仕事に取り組んでいた。あれをただのワーカホリックと言われても説得力がないように思う。
他に何の実績のないマヤにとって、この仕事だけが存在理由だとほのめかすシーンもあるが、わりとそっけない演出で終わるし、なによりそのシーンは物語の終盤だ。普通動機の提示は冒頭に来るのが普通。
でも、おそらく多くのアメリカ人の観客にとってはそんな説明は不要かもしれないと思った。上述の疑問を誰かにぶつけても、きっとこう返されて終わりかもしれない。
「だって相手はあのビン・ラディンだぜ。当然だろ」
同様にビン・ラディン殺害のプロセスで疑問にいくつかある。バキスタンの都市の郊外の隠れ家にビン・ラディンが潜んでいるとう確実な情報がないにも関わらず、アメリカは殺害作戦を実行に移した。映画の中の台詞で言えば、「イラクの大量破壊兵器の時だって、もっとマシな情報だった」にも関わらず、アメリカは決行した。
その薄弱な根拠だけで、あの重大な決定はどのような政治力学でなされたのかは描かれない。これも普通の映画ならあり得ないのではないか。でも「相手はあのビン・ラディン」ということで納得するのかもしれない。
あの弱い状況証拠だけで殺害作戦を決定する過程を描かないのは、アメリカという国がどうしてもビン・ラディンをぶっ殺したいという執念の表れということなのか。
そもそもパキスタンの民間の家に米軍が武装ヘリで急襲するという、超法規的措置がどうしてまかり通っているのかも描かれない。実際異変を聞きつけたパキスタン軍が現地に緊急出動し、米軍は追われるように撤退するわけだが、あれをどう正当化されるのか、きちんと描かれていない。でもきっとその疑問も「相手があのビン・ラディン」なので、アメリカ国内では特に疑問に思われないのかもしれない。キャスリン・ビグロー監督以下、製作陣が作戦の詳細を記した国家機密へのアクセスを許可された云々、という報道もあったが、監督や脚本家がどこまでその作戦の詳細を把握しているのかわからないが、製作陣はそこを描く必要がないと判断したのだろう。
なぜなら「相手はあのビン・ラディン」だからみな納得すると思ったのではないか。
世界を舞台にアメリカの国内問題を描く作品をどう捉えるべきか
『ゼロ・ダーク・サーティ』は、アフガン、パキスタン、クウェートなど中東を舞台にアメリカの10年の国内感情を描く映画だ。アメリカを知る、という意味ではとてもいい映画だ。アメリカのその内省的な視座を学ぶという意味で。
アメリカ人にとっては、9.11以降、狂った時代の総括と反省としても意義のある作品ということになるかもしれないが、日本人の僕が同じ評価を下すわけにもいかない。ビグローはハート・ロッカーの時を変わらず内向きの視点でのみ、この問題を見つめていた。果たしてそれでいいのか。
ちなみにアメリカの映画レビューサイト、Rotten Tomatoesでの支持率は94%。オスカー候補作の中ではアルゴの96%に次いで、2番目に高い数字だ。
手持ちカメラの映像とケン・ローチ組のサウンド、レイ・ベケットを始めとするサウンド陣の素晴らしい音響効果、ジェシカ・チャスティンの名演など、映画としての見所はとても多い作品。サスペンス映画としては一級品だ。
公式サイト。
映画『ゼロ・ダーク・サーティ』公式サイト
予告編はこちら。
関連記事;
映画パンフレビュー「ゼロ・ダーク・サーティ」
アカデミー賞監督、キャスリン・ビグローがVRの短編ドキュメンタリーを制作




